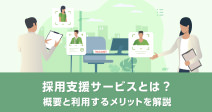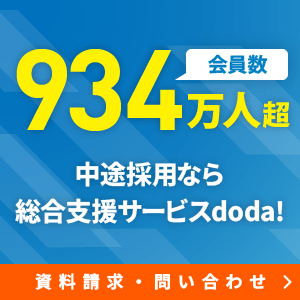2025.05.02
中途採用のキホン
採用での売り手市場が続く昨今では、即戦力となる人材を採用できるかどうかが企業の将来を左右する、といっても過言ではありません。「しかし、どうすれば自社に即戦力の人材を採用できるのか…」とお悩みの人事・採用担当者にお勧めの方法が、キャリア採用です。
本記事では、キャリア採用の概要や重要性とともに、利用が適している職種なども解説します。該当する職種で活躍が見込める人材をお探しであれば、ぜひご覧ください。

キャリア採用とは
キャリア採用とは、就業経験があり、かつ自社業務に関する経験やスキルをすでに持っている人材を採用することです。特に、ITエンジニアやモノづくり系エンジニアなど、経験・スキルの有無が重要となる職種で即戦力が必要な場合には、最適な手段となり得ます。
実際にキャリア採用を行う際は、応募条件として「○○の業務経験」「マネジメント経験」などを設定することが一般的です。この特性上、未経験者でも応募できる求人や、意欲・将来性を重視するポテンシャル採用などは、キャリア採用とは正反対の手段だといえるでしょう。
キャリア採用と中途採用の違い
就業経験がある人材を採用する方法としては、ほかに「中途採用」も挙げられます。キャリア採用とほとんど同じであるように思えますが、実際には、中途採用という大きな枠組みの中にキャリア採用が存在する関係性となっています。この点は大きな違いとなるため、きちんと把握しておきましょう。
先ほど説明した通り、キャリア採用では特定の業務に関して十分なスキルを持つ人材を採用します。一方で、中途採用は「就業経験がある」という要件さえクリアしていれば応募が可能です。よって、第二新卒や業種・業界未経験の人材も採用の対象となります。
このように、キャリア採用と中途採用は対象となる人材の範囲が異なっているため、自社の状況に応じて使い分けなくてはなりません。即戦力が必要な状況では、「経験者のみ」と応募条件を定めるキャリア採用が最適です。対して、経験やスキルの有無にかかわらず人材が必要な場合には、間口を広げるためにも中途採用として募集をかけることをお勧めします。
キャリア採用が注目を浴びている背景
近年、キャリア採用を導入する企業が増えつつあります。しかし、なぜキャリア採用はそこまで注目されているのでしょうか?そこには、以下に解説する2つの事情が大きく関係しています。
転職が一般的になったため
キャリア採用が注目されている大きな要因の一つとしては、転職という選択肢が一般的になったことが挙げられます。
かつての日本では、新卒で入社した会社に定年まで勤める「終身雇用」が、働き方として定着していました。しかし、日本経済の停滞や少子高齢化、または技術革新などのさまざまな要因によって、終身雇用に固執しない働き方が徐々に浸透していったのです。こうした経緯があり、キャリアアップを目指して、あるいはワークライフバランスを重視して転職することが日本でも一般的となりました。
しかし、転職希望者は増えている一方で、少子高齢化の影響による人手不足の問題は依然として解決できていません。このような状況下で、「即戦力を採用したい」と考える企業も増加し、近年では転職市場での競争は激化の一途をたどっています。多くの企業がキャリア採用に注目している背景には、こうした事情があります。
即戦力が必要な場面が増えたため
即戦力となる人材が欠かせない場面が企業で増えたことも、キャリア採用が注目されている要因の一つです。
経済環境や技術革新など、現代では多種多様な要因で市場が変化していきます。そうした急速な変化に企業が対応するためには、各種領域に精通した専門家やスペシャリストの存在が必要不可欠です。もちろん、自社内で専門家を育成することも可能ですが、それだけでは市場の変化に追いつけず、競合他社に後れを取ってしまうかもしれません。
そこで重要となる施策が、キャリア採用です。キャリア採用で経験やスキルのある人材を採用できれば、スピーディーに自社の体制を強化できます。市場の変化に合わせて自社を成長させたいのであれば、キャリア採用を有効活用しましょう。
キャリア採用が向いている職種
ここからは、キャリア採用での募集が適している職種を紹介します。以下の7つの職種に該当する人材を採用したい場合には、キャリア採用の活用をご検討ください。
ITエンジニア
技術の発展が目まぐるしいIT領域では、常に最新の情報をキャッチアップし対応できる人材が求められます。高い技術力も備えている必要があるため、社内で一から育成するよりもキャリア採用を活用するほうが効果的です。実際、転職市場でもITエンジニアの求人数は多く、その需要の高さがうかがえます。
なお、ITエンジニアとひと口にいってもその種類は多岐にわたるため、実際に募集する際は分野を指定する必要があります。最近では、人工知能(AI)やデータサイエンス、クラウドコンピューティングなどの重要性が増しているため、対応できる人材をキャリア採用で優先的に募集したいところです。
モノづくり系エンジニア
技術力が必要で、即戦力の重要性が高い職種としては、モノづくり系エンジニアも挙げられます。
モノづくり系エンジニアとは、製造業全般に従事する人材のことです。具体的には、自動車や産業機械、電気機器、半導体、ソフトウェア機器などの製造に携わる人材が該当します。デジタル化の進む現代ではありますが、こうしたモノづくりの重要性も依然として高く、特に産業用ロボットや半導体分野などは大きな注目を集めています。
先ほど紹介したITエンジニアと同様に、モノづくり系エンジニアにも高度な技術力が必要不可欠です。また、予期せぬトラブルが発生した際の対応力も必要であるため、実務経験も欠かせません。キャリア採用は、上記の要件を満たす人材を探す上で最適な選択肢といえるでしょう。
新規事業開発
キャリア採用は、新規事業開発、つまり自社で新しいビジネスを始めたい企業にもうってつけです。
既存事業で培ってきたノウハウだけで、新規ビジネスを立ち上げることは容易ではありません。新たに進出する市場の状況や競合他社の動向、必要となる技術など、多種多様な観点でデータを収集・分析し、準備を進める必要があります。その際、新規ビジネスに関連する経験やスキルを持っている人材をキャリア採用すれば、準備にかかる時間や費用を大幅に削減できるはずです。
キャリア採用を活用し、即戦力となる人材を適材適所で採用すれば、新規ビジネスでも好調なスタートを切れるでしょう。
営業
経験とスキルの有無が業績に直結する営業も、キャリア採用で人材を探したいところです。
営業のノウハウは一朝一夕で身に付くものではないため、自社内の教育だけで対応することは、容易ではないでしょう。その一方で、営業活動の成否は企業の未来を左右する重大な要因であるため、第一線で活躍できる人材も欠かせません。キャリア採用で十分な営業スキルのある人材を採用すれば、上記の課題を同時に解決できます。
新規顧客の開拓や大手企業との取引を検討中なのであれば、キャリア採用で即戦力となる営業担当を募集しましょう。
経理・財務・法務・人事
経理や財務、法務、人事などは特定分野の知識が要求されるため、未経験者に任せることは、不可能とまではいかないものの現実的ではありません。例えば法務などは、法律に関する知識やトラブルに対処するためのノウハウが求められます。人事に関しても、転職希望者を見極める力や、複数の業務を効率的にこなす対応力が必要です。これらの業務で人手不足が発生しているなら、キャリア採用による解決が効果的でしょう。
また、バックオフィス業務の内容は企業ごとに大きな差が出にくいため、入社して間もない人材でもすぐに現場に慣れてくれる可能性があります。この点も、キャリア採用の有用性を後押ししているといえます。
マーケティング
商品やサービスのプロモーション、またSEO対策・SNS運用などを任せるマーケティング担当者に関しても、キャリア採用の活用が適しています。
マーケティングでは、消費者の行動や市場を分析する能力が必要です。さらにデジタルマーケティングともなると、検索エンジンに関する知識やITに関連するノウハウも求められます。
マーケティングを専門としている企業でない限りは、そのようなスキルを備えた人材の育成はあまり現実的ではないでしょう。マーケティングもスピード感が重要であるため、キャリア採用で効率良く人材を採用するほうが効果的だといえます。
クリエイティブ系職種
キャリア採用が適した職種としては、デザイナーやWebディレクターをはじめとするクリエイティブ系も該当します。
イラストの作成や広告のデザイン、キャッチコピーの作成、またWebサイトのディレクションなどは、いずれも高い専門性が要求されます。また、状況に応じたフレキシブルな対応が必要となることが多いため、知識のみならず実務経験に基づく応用力も備えていなくてはなりません。
「デザイン性の高い広告やポスターを内製したい」「自社サイトの独自性を高めたい」とお考えなら、キャリア採用で十分な経験・スキルのある人材を採用しましょう。
キャリア採用を行うメリット
ここで改めて、キャリア採用を行うことで得られる4つのメリットを説明いたします。キャリア採用のメリットを理解することが、より効果的な運用につながります。
メリット①即戦力となる人材を採用できる
ここまでで触れてきた通り、即戦力を効率良く採用できることがキャリア採用の大きなメリットとして挙げられます。
特定領域に関して十分なスキルを備えているため、キャリア採用の人材には入社直後からの活躍が期待できます。新卒採用や未経験者の中途採用では教育が必要となるため、キャリア採用ほどスピーディーに成果を出すことは難しいでしょう。
特に、急ぎ完遂しなくてはならないプロジェクトがある場合には、品質を維持しつつスピーディーに対応するためにも、キャリア採用で即戦力を採用したいところです。また、従業員の退職による人手不足に対しても、キャリア採用は有効な解決策となり得ます。
メリット②教育にかかる費用や時間を抑えられる
人材の教育にかかるコストをある程度抑えられる点も、キャリア採用を実施するメリットの一つです。
未経験者を採用する場合は、社内研修やOJTなどで一から教育しなくてはならないため、どうしても費用と時間がかかってしまうものです。もちろん、未経験者の教育も大切なことではありますが、状況によってはそこまでリソースを割けない場合もあるでしょう。
その点、キャリア採用で募集した人材は、すでに社会人としてのマナーや業務に関する知識を備えているため、教育にかかるコストをある程度抑えられます。ただし、自社独自のルールや顧客の情報などは覚えてもらう必要があるため、まったく教育しなくてよいわけではありません。この点は人材の定着に大きく関わってくるので、人事・採用担当者は把握しておきましょう。
メリット③新たなノウハウを取り込むことができる
キャリア採用で募集する人材は、それまでの経験で業務に関する深い知識やスキル、社会人としての考え方などを培ってきているはずです。そこから、新しいノウハウ・価値観を自社に取り込めることも、キャリア採用によって得られるメリットだといえます。自社に足りていなかった部分を補強できれば、成長が停滞気味であった組織を活性化させられるかもしれません。
また企業戦略の面でも、新しい知見を得られることは大きな強みとなり得ます。特に、将来的なビジネスチャンスのある領域に精通している人材を採用すれば、競合他社に対して大きくリードできるでしょう。
メリット④組織の生産性向上につながる
キャリア採用によって新しいノウハウや価値観を組織に取り込むことは、生産性の向上にもつながります。それまでになかった観点から、業務効率化のヒントや課題解決の足掛かりを得られるためです。例えば、自社サービスの利用者数が伸び悩んでいる企業であれば、キャリア採用で入社した人材の第三者的な視点を取り入れることで、その状況を打開できる可能性があります。
上記のほか、経験者を採用したことによる業務の効率化や、シンプルな人手不足の解消など、生産性の向上につながる要因は多岐にわたります。生産性に関して課題を抱えているのであれば、キャリア採用を検討してみてはいかがでしょうか。
キャリア採用を行うデメリット
企業に多くの恩恵をもたらしてくれるキャリア採用ですが、懸念点も存在するので把握しておきましょう。具体的には、以下の3つがデメリットとして挙げられます。
デメリット①採用費用がかかる
一定の経験やスキルがある人材の給与水準は、未経験者のそれよりも当然高い傾向にあります。よって必然的に、キャリア採用で発生する採用費用も高くなってしまうのです。また、専門職や管理職クラスの人材を採用するケースだと、人材紹介サービスなどの手数料も高くなる場合があり、さらに費用がかかるかもしれません。
とは言え、採用費用をあまりにも抑えると、要件を満たす人材を集めることが難しくなってしまいます。求める経験やスキル、そして転職市場の動向を加味して、適切なラインで予算を決めたいところです。
デメリット②パフォーマンスを発揮できない可能性がある
活躍を期待して採用した人材が、想定していたほどのパフォーマンスを発揮できない可能性がある点も、キャリア採用の無視できないデメリットです。
キャリア採用で入社した人材は、高い水準のスキルや知識を持っているはずなので、当然活躍するものと思われるかもしれません。しかし、自社の社風になじめなかったり、既存社員との人間関係をうまく構築できなかったりすると、スキルのある人材でもパフォーマンスを発揮することは難しいのです。このような事態が発生すると、社内の業務効率が低下するだけではなく、採用した人材が早期退職してしまう恐れもあります。
キャリア採用の人材は、すでに自分のやり方や考え方が確立されていることが多いため、上記のようなミスマッチが生じる可能性が高いといえます。採用の際は、経験やスキルだけではなく、自社の雰囲気に合うかどうかもしっかりと見極めることが大切です。
デメリット③既存社員と摩擦が発生することがある
即戦力として採用した人材と既存社員との間で、過度な競争意識が生じるケースもあります。特に、新しく入社した人材のポジションが既存社員と重なっていると、強い対抗意識が芽生えて不和を生んでしまうかもしれません。
この問題を放置すると会社に対しても不満がたまり、最終的には社員が退職するという事態に発展しかねません。キャリア採用の人材もフォローしつつ、既存社員に対しても明確なキャリアプランを示すなどして、それぞれの抱える懸念点を解消できるように努めましょう。
【選考時】キャリア採用を成功させるためのポイント
メリットもデメリットもあるキャリア採用ですが、実践時にいくつかのポイントを意識すれば成功する可能性を高められます。ここではまず、選考時に意識したいポイントを解説します。
ポイント①採用背景から求めるスキルを明確にする
キャリア採用では、その目的と人材に求めるスキルを明確にすることが非常に重要です。
キャリア採用で募集する人材に期待する役割が定まっていなければ、必要な経験やスキルも当然決められません。そのような状況では、多数の転職希望者の中から自社に合った人材を選ぶこともできないでしょう。また、人材を採用できたとしても、自社が本当に必要としていた要件を満たせず、活躍が見られないまま早期退職してしまう可能性があります。
このような事態を避けるためにも、まずは採用要件を社内で詳細に定義しましょう。その際は、業務に関わるスキルや知識だけではなく、仕事に対する考え方や行動特性なども明確に定められると理想的です。
ポイント②自社の情報を可能な限り発信する
自社の情報を少しでも多く、そして詳細に発信することも、キャリア採用を成功させるためには欠かせません。
キャリア採用では、転職希望者側も自身に合う企業を選定しています。自社を検討候補に含めてもらうためにも、まずは以下の情報を詳細に発信していきましょう。
情報を発信する際に含めたい内容
- 競合他社にない自社だけの魅力
- 企業理念やミッション
- 社風や企業カルチャー
- キャリアプランの具体例
- 給与や福利厚生などの労働条件
ただし、良い部分だけを発信してしまうと、入社後に「想像していた職場と違う」とギャップが生じかねません。採用のミスマッチが発生しないように、自社の長所と短所をバランスよく発信することが大切です。
ポイント③労働条件などの自社課題は早めに改善する
求める人材像を定めて自社の情報を発信したとしても、転職希望者が応募してくれるとは限りません。給与水準や残業時間といった労働条件、あるいはそのほかの自社課題が残ったままでは、活躍が見込める人材は集まらないでしょう。
積み残している課題にもし解決できる見込みがあるなら、早急に対処することをお勧めします。一方で、給与水準などの一部の課題は、即座に手を打てるものではありません。そうした課題が残る場合は、例えばフレックスタイム制を導入するなど、別の施策によってカバーしましょう。
ポイント④選考プロセスを改善する
「転職希望者が集まり始めたが、選考を辞退する人数も多い…」という状況であれば、選考プロセスを一度見直すことをお勧めします。
キャリア採用をはじめとする中途採用では、基本的に選考は短いほうが良いと考えられています。選考が長引くと、その間に人材が他社へと流れてしまうためです。「最終選考までに何カ月もかかっている」「選考と選考の間が空き過ぎている」など、思い当たる節があるなら、選考期間の短縮を図りましょう。
選考期間の長期化は、情報連携の体制ができていないことやスケジュール調整の遅れなど、選考プロセスに関わる部分に原因があると考えられます。よって、選考の手順や関係各所の協力体制を見直すことが、効果的な対策となるでしょう。
【入社後】人材に定着・活躍してもらうためのポイント
キャリア採用のゴールは、自社が求める人材を採用することではありません。採用した人材が定着し長く活躍し続ける状況こそが、実現すべき目標だといえます。
この目標を達成するためにも、キャリア採用の人材が入社したあとは、以下の3点を意識してサポートを行いましょう。
ポイント①オンボーディング施策を行う
採用した人材の早期退職を防ぎ、パフォーマンスを発揮できる環境を整える上で重要となる施策が「オンボーディング」です。
オンボーディングとは、新たに入社した人材が職場に慣れて、活躍できるようにするための取り組み全般を指すものです。具体的には、企業理念やルールといった基本情報の説明や、実業務を通じた研修などが挙げられます。入社した人材が会社にしっかりとなじめるように、数カ月~1年程度は実施しましょう。
なお、さまざまなプログラムに取り組む関係上、オンボーディングでは事前準備が非常に重要なフェーズとなります。新しい環境で不安を抱えるキャリア人材を手厚くサポートできるように、早い段階から受け入れる体制を整えておきたいところです。
ポイント②社内で人間関係を構築できるようフォローする
既存社員とスムーズに関係を築けるようにフォローすることも、入社後のサポートとしては必要不可欠です。
当然ですが、キャリア採用で入社した人材は、社内の人間関係について何も把握していません。そのため、業務中にわからないことがあったり悩みを抱えていたりしても、相談すべき相手を見つけられず、ストレスを抱えてしまう可能性があるのです。
本人の不安や心配を軽減するためにも、人事・採用担当者が積極的に人間関係についてフォローしましょう。具体的には、入社祝いの歓迎会を開く、または業務で関わる社員にあいさつする時間を設けることなどが解決策として挙げられます。
ポイント③入社後の役割・ミッションを擦り合わせる
「自分の役割はこれで合っているのか」「会社の方針に沿えているのだろうか」といった不安を人材が抱えたままでは、十分なパフォーマンスを発揮できません。そのため、キャリア人材に求めているスキル・期待している振る舞い方を入社後に改めて伝えて、擦り合わせを行うことも大切です。
認識を合わせた上で、もしキャリア人材が自身の役割と現状のギャップに悩んでいそうであれば、上司や先輩社員が1on1を行いサポートしてあげましょう。キャリア人材が抱える悩みを解決できるだけではなく、コミュニケーションの活性化や関係性の構築にもつながります。
キャリア採用の手順
キャリア採用を行う際の基本的な進め方は、以下の通りです。
キャリア採用の基本的な手順
- 求める人材像を明確にする
- 採用手法を決める
- 選考基準を決める
- 募集を出して採用活動を進める
- 選考~入社前後のフォローを行う
- 課題を洗い出して改善する
各ステップの詳細を、以降で確認していきましょう。
ステップ①求める人材像を明確にする
キャリア採用の実践時にまず取り組むべきことが、求める人材像の明確化です。
先ほどもお伝えした通り、転職希望者に求める経験やスキルが定まっていなければ、自社に合った人材を探すことは難しいでしょう。「どの業務を任せるのか」「社内でどのように振る舞ってほしいか」といったポイントを整理し人材像を明確にすることが、キャリア採用では必要不可欠です。
またその際は、現場の意見も必ず取り入れましょう。現場の社員と人事・採用担当者の間で求める人材像に乖離(かいり)があると、採用に至っても人材が現場になじめず、すぐに退職してしまうためです。関係者間で人材に求める要件を擦り合わせて認識を統一すれば、こうした採用のミスマッチが減り、定着率の改善につながります。
ステップ②採用手法を決める
人材像の明確化が完了したら、予算やスケジュールなども加味した上で採用手法を決めていきましょう。キャリア採用を行う際に用いられる採用手法としては、主に以下が挙げられます。
キャリア採用の代表的な採用手法
- 人材紹介サービス
- ダイレクト・ソーシング
- 求人情報サイト
- 自社の採用サイト
- SNS
上記はそれぞれ適しているケースが異なるため、自社の状況や目的に合わせて選定する必要があります。複数の手法を併用して、多面的に採用活動を進めるという戦略を取ることも可能です。
ステップ③選考基準を決める
採用手法が決まれば、求人を出して実際に採用活動を始められますが、その前に社内で選考基準を決めておかなくてはなりません。面接官ごとに選考基準が異なっていると、公平な評価ができず、採用のミスマッチにつながってしまいます。
選考基準を検討する際は、最初に決めた「求める人材像」の条件をベースにすることをお勧めします。培ってきた経験・スキルや資格、コミュニケーション力などの要素がどの程度のレベルであれば、自社の要件を満たすのかを決めましょう。ここで具体的な選考基準を定められれば、自社で長く活躍してくれる人材を採用できる可能性を高められます。
ステップ④募集を出して採用活動を進める
採用手法と選考基準の両方が決まり次第、求人募集をかけて採用活動を始めます。
転職希望者に興味を持ってもらえなければ、応募数が増えることはないでしょう。よって、求人を出したら受け身で応募を待つのではなく、自社から積極的に情報を発信することが大切です。募集要項に業務内容や労働条件などを詳細に記載する、またはホームページやSNSなどで情報を更新するなどの試みが効果的です。昨今の転職希望者が重視していること・企業に求めていることを分析した上で、それに応えられるような情報を発信しましょう。
ステップ⑤選考~入社前後のフォローを行う
応募があった転職希望者に関しては、まず履歴書や職務経歴書を確認します。そこで「要件に合いそうだ」と思えたのであれば、面接でより詳細に適性を見極めます。
面接の際は、履歴書の情報からは判断できない人となりや雰囲気、考え方などを深掘りすることが大切です。経験・スキルの有無がキャリア採用の軸ではありますが、性格や気質が自社と合わなければそもそも定着が見込めないためです。人間性や性格などを重点的にチェックして、自社に合う・合わないを早い段階で見極めていきましょう。
選考が進んで合格となり、転職希望者からも入社の承諾を得られたら採用となります。しかし、人事・採用担当者の仕事はここで終わりではありません。転職希望者の不安や懸念点を払拭するために、入社前後のフォローを行う必要があります。ここで手厚いサポートを提供できれば、採用した人材が早々に離職してしまう可能性を減らせるでしょう。
ステップ⑥課題を洗い出して改善する
採用活動が終了したら、キャリア採用の成否にかかわらず振り返りを行い、課題を洗い出します。特に人材の採用に至らなかった場合には、どこに課題があったのかを関係者間で入念に話し合い、改善しましょう。良かった点に関しては、以降の採用活動がより実りあるものとなるように、採用ノウハウとして蓄積したいところです。
このようにPDCAを回して、採用活動の質を徐々に高めていくことが、自社の要望に合致する人材の採用につながります。
キャリア採用をdodaが支援した事例
最後に、企業のキャリア採用をdodaが支援した事例を紹介します。キャリア採用を行う際は、これらの事例をぜひご参考ください。
dodaのサポートを受けて150人もの即戦力を採用|SOMPOホールディングス株式会社
多種多様な領域を手掛けているSOMPOホールディングス株式会社は、転職希望者に「既存事業」のイメージを強く持たれてしまうことを、課題として抱えていました。新たな領域へと積極的に進出している最新の姿を伝えていくためにも、同社は人材を必要としている部門に採用権限を委譲し、現場主体で採用活動に臨んでもらう方針へとかじを切ります。
本施策の実践時にはdodaがサポートに当たり、各部門の担当者との協力体制を構築。リクルーティングアドバイザーや、キャリアアドバイザーが現場の担当者とミーティングし、人材要件の整理を進めました。その結果として、3年間で150人もの即戦力を採用することに成功します。
ゼネラリスト人材を採用するためにdoda人材紹介を活用|株式会社スプリックス
個別指導塾を祖業とする株式会社スプリックスは、新規事業の展開を進める中でキャリア採用の強化に取り組み始めます。
同社には、「教育の現場で活躍したい」という思いを抱く人材は多い一方で、コーポレート系職種など「ゼネラリストとしてキャリアを積みたい」という考える人が少ないのが現状でした。そこで、これらの領域をカバーできるゼネラリストを、doda人材紹介で募集することに決定します。
dodaからは、キャリアアドバイザーをはじめとする複数の担当者をアサイン。所属部署や担当領域を超えた協力体制を築き、さまざまな観点から最適な採用手法を模索しました。こうした取り組みが功を奏し、異業種出身の転職希望者からの応募が増えた結果、複数のゼネラリスト人材を採用できたそうです。
dodaとの二人三脚の協力体制でキャリア採用に取り組む|DIC株式会社
印刷インキや有機顔料などの分野で世界をリードしているDIC株式会社も、doda人材紹介でキャリア採用を実現した企業の一つです。
同社はエネルギーやヘルスケア領域にも取り組んでおり、この領域で活躍が見込めるハイクラス人材を必要としていました。同領域での採用を目指して、dodaではまず転職市場を分析した上での要件定義を実施。現場の要望をしっかりと反映しつつも、実現可能な採用基準を設定しました。
また、dodaが紹介した人材に関するフィードバックは、DIC株式会社から素早く共有され、それを受けて、dodaからは「こうした人材が本当は必要なのでは?」と提案を行う、という協力体制を構築できており、現在も二人三脚でキャリア採用に取り組んでいます。
初のダイレクト・ソーシングをdodaのサポートとともに実施|岸和田製鋼株式会社
求人広告にかかる費用が大きな課題となっていた岸和田製鋼株式会社は、応募人数が増えても費用が変わらないdoda ダイレクトを導入。「かえって工数が増えるかもしれない」という不安もあったそうですが、dodaの徹底したサポートによりその懸念は払拭できました。
doda ダイレクトの運用開始後は、約2週間で1名、3カ月で営業職・事務職などでも数名の採用に至っており、早い段階で結果につながっています。また、doda ダイレクトとの取り組みを通じて、会社全体で転職市場についての知見を深められたことで、求人広告の見直しを図ることもできたそうです。
キャリア採用を活用して即戦力を採用することが、企業の発展につながる
今回は、キャリア採用の概要やメリット・デメリットなどを解説しました。
キャリア採用とは、特定の業務に関する経験・スキルを持つ即戦力を採用することです。自社の強化を図りつつも教育コストは抑えられるため、急ぎ人材が必要なケースや、新規事業を始める際には最適な採用方法となり得ます。実践に際しては、選考時と入社後のそれぞれのフェーズで意識するべきポイントがあるため、その点は事前に把握しておきましょう。
キャリア採用に関して何か困りごとがあれば、人材紹介サービスやダイレクト・ソーシングを提供しているdodaにぜひご相談ください。転職市場に精通した担当者が、多面的な視点から課題の解決に当たります。

採用コスト削減につながった
doda導入・採用成功事例
おすすめ記事
キャリア採用とは?中途採用との違いや手順・採用成功のポイントを解説ページです。【中途採用をお考えの法人様へ】dodaサービスのご案内 - 採用成功への扉を開く、総合採用支援サービス