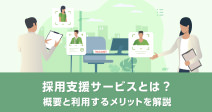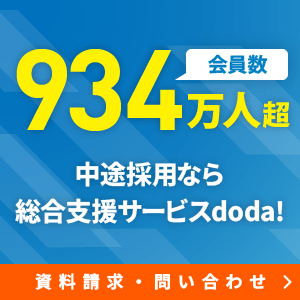2025.07.28
中途採用のキホン
「社会人経験者を採用したいけれど、中途採用がなかなかうまくいかない…」
このようなお悩みを抱えていませんか?
中途採用は、昨今の市況が影響し、難易度が高くなりつつありますが、適切なポイントを押さえれば、自社に合う人材を効率的に採用できます。
そこで本記事では、中途採用が難しくなっている理由や、採用にあたって押さえるべきポイントなどを解説します。中途採用に難航している人事・採用担当者はご覧ください。

中途採用が難しい理由
中途採用がうまくいかない理由には、「市況などの外部要因」と「自社が抱えている課題という内部要因」の両方があります。具体的には、以下の7つが理由として考えられます。
中途採用が難しい理由
- 中途採用市場が売り手市場のため競争が激しい
- 即戦力となる人材の採用の競争激化
- 転職希望者の仕事に対する価値観の多様化
- 人材の見極めが難しい
- 企業の魅力や強みが伝えられていない
- 採用手法が多様化していて選定が難しい
- 採用活動のリソースが限られている
中途採用市場が売り手市場のため競争が激しい
近年、中途採用市場は転職希望者数よりも求人数のほうが多い「売り手市場」となっており、その状況が採用の難度に影響を与えていると考えられます。dodaが実施している調査でも、転職求人倍率が年を追うごとに右肩上がりとなっており、高い水準が続いていることがわかっています。
売り手市場の大きな問題は、人材を求める企業同士の競争が激化し、「転職希望者に選ばれない」企業が増えることです。たとえ求人を出しても、自社よりも魅力的な条件を提示できる競合他社や、ネームバリューのある大手企業に転職希望者が流れてしまうことがあります。
(参照:『doda転職求人倍率レポート』)
即戦力となる人材の採用の競争激化
上述の「売り手市場」により、即戦力となる人材の採用は特に難しくなりつつあります。そのため即戦力を求めている企業は、中途採用の難しさを実感しているのではないでしょうか。
元々、新卒採用や未経験者を対象とした中途採用よりも、即戦力となる人材を対象とした中途採用のほうが難しくなる傾向にあります。なぜなら、特定の経験がなくともポテンシャルさえあれば母集団を形成しやすい前者に対し、後者はそもそも一定の経験やスキルを求めている関係上、母集団形成がなかなかスムーズにいかないためです。
また、多くの企業にとって、教育コストのかからない即戦力となる人材のほうが需要が高いことも、採用が激化する一因となり得ます。
転職希望者の仕事に対する価値観の多様化
中途採用が難航する外的要因としては、転職希望者の価値観が多様化しつつあることも挙げられます。コロナ禍以降は、リモートワークやフレックスタイム制、時短勤務など、さまざまなはたらき方が注目されるようになりました。これは、「doda」が独自に行った調査でも同様のことがわかっています。
「doda」の「フリーワード検索」ランキングを、コロナ禍初期の2020年5月と、2025年4月で比較してみましょう。
doda「フリーワード検索」ランキング
| 2020年5月 | 2025年4月 | |
|---|---|---|
| 1 | 50代 | 在宅勤務 |
| 2 | 英語 | フルリモート |
| 3 | 中国語 | 工事 |
| 4 | 未経験歓迎 | 建築士 |
| 5 | 未経験 | 電気工事士 |
このほか、「副業」というキーワードは2020年5月の段階ではトップ100圏外でしたが、2025年4月には25位になっているという変化も起きています。このようなはたらき方への価値観の多様化により、中途採用の「勝ちパターン」も従来とは異なってきていることで、採用が難しくなっていると考えられます。
(参照:『人気の検索キーワードランキング』)
人材の見極めが難しい
中途採用の難しさとして、「自社で適切な人材を見極めて採用することが難しい」といったことも挙げられます。
基本的にはポテンシャルで判断する新卒採用に対し、中途採用ではポテンシャルだけでなく、転職希望者のもつスキルや経験も見極める必要があります。経歴や業務経験は採用条件と一致している転職希望者でも、実際に現場で発揮できるスキルはレベルに達していなかった…といったこともあるでしょう。
書類選考や面接だけでは、「自社で本当に活躍できる人材か」を見極めることが難しいという課題が、中途採用の難しさに影響を与えています。
企業の魅力や強みが伝えられていない
知名度が低い企業の場合、「転職希望者に自社の魅力がなかなか伝わらない」といった難しさもあります。
売り手市場である昨今では、同じような業務内容・条件であれば、転職希望者は知名度のある企業を選ぶことが考えられます。結果、知名度の低い企業には応募が集まらない、あるいは入社承諾前辞退が起きてしまうのです。
採用手法が多様化していて選定が難しい
近年は、求人広告だけでなく、ダイレクト・ソーシングや人材紹介サービス、SNS採用など、
さまざまな採用手法が各企業で取り入れられています。つまり、一つの採用手法に頼るだけでは、十分な応募数を獲得できない可能性があるということです。
そのため「自社に合う採用手法がどれなのかがわからない」といった課題も現れていることが考えられます。
採用活動のリソースが限られている
採用活動には、さまざまな工程があります。しかし、主業務と並行して採用活動に割けるリソースが限られているがゆえに、思うように進められない…という悩みを抱えている人事・採用担当者もいるでしょう。
中途採用では、急な退職や業務量の増加による欠員補充が求められる傾向にあります。つまりスケジュールが決まっている新卒採用と異なり、採用活動のスケジュールが読めず、突発的に、可能な限り短期間で新しい人材を見つけなければならないということです。
そういった状況下では、限られたリソースで転職希望者の適正を見極められず、ミスマッチを起こしてしまう…といったことも起こり得ます。
中途採用でありがちな失敗例
上記のような課題を抱えている中途採用では、課題が多いがゆえの失敗が起こる可能性があります。具体的には、以下の4つの失敗例がよく見られます。
中途採用でありがちな失敗例
- 採用計画や要件が定まっていない
- 母集団形成が十分にできていない
- 入社承諾前辞退が頻繁に発生している
- 入社後の定着率が低く早期離職をしてしまう
採用計画や要件が定まっていない
採用計画や要件があいまいになっていると、中途採用が思うように進まず、このあと取り上げる失敗例につながる可能性があります。
採用活動を進めるには、「いつまでに、何人採用するのか」といった採用計画とともに、「自社はどのような転職希望者を求めているのか」という要件を定めることも欠かせません。必要な情報があいまいだと、関係者間でも認識を統一できず、採用のミスマッチが生じてしまいます。
母集団形成が十分にできていない
必要な応募数が集まらない、つまり母集団形成が十分にできていないケースは「失敗」といえるでしょう。母集団形成ができなければ、その後の選考フローに進む転職希望者の人数も限られてしまうため、自社とマッチする人材と出会える可能性が下がります。
特に、知名度が低い中小企業は、大手企業に人気が集まることで母集団形成に苦戦する傾向があります。
関連記事:「母集団形成とは?採用手法と手順、課題ごとの解決策を解説」
入社承諾前辞退が頻繁に発生している
たとえ、自社の求めている人材と出会えて、採用条件通知書を出したとしても、転職希望者が入社承諾前に辞退してしまう…といったことも起こり得ます。辞退が頻発している場合は何らかの問題が発生していると考えるべきでしょう。
入社承諾前辞退が起きる原因には、やはり「売り手市場」の市況が関係しています。多くの転職希望者は複数の企業の選考を並行して受けているため、自社よりも魅力的な条件の企業があればそちらに集まってしまうのです。
このような問題は、たとえ母集団形成を十分に行えていたとしても起きる可能性があります。
入社後の定着率が低く早期離職をしてしまう
母集団形成や入社承諾前辞退の問題をクリアした上でも、入社後の早期離職が相次ぐ…という事態が起きることがあります。無事に人材を採用できたあとに起きるので、採用活動とは一見無関係に思えるかもしれませんが、こちらも「中途採用の失敗」の一つです。
なぜなら、採用のミスマッチが起きることで早期離職につながるためです。また、入社後のフォローが不十分であることも理由として考えられます。
いずれの場合でも、「とにかく人材を採用したい!」という余裕のない状況での判断がこのような失敗につながることは覚えておきましょう。
中途採用がうまくいかないときの改善策
上記の失敗例を踏まえた上で、中途採用に難航しているときの改善策をご紹介します。
中途採用がうまくいかないときの改善策
- 採用計画や基準を見直す
- 採用手法の見直しや他の採用手法を試す
- 採用ブランディングを行う
- 労働条件や待遇を改善する
- 採用フローの短縮化や見直し
- 入社後のフォローを徹底する
- 外部のサービスを活用する
採用計画や基準を見直す
中途採用を成功させるために、まずは採用計画や採用基準を見直しましょう。採用計画を見直すにあたっては、前年度の実態を振り返った上で、良かった点や改善点を明確にします。そうすると、具体的な改善点が浮かび上がってくるはずです。
また、市場や競合の現状をリサーチすることで、転職希望者にとって魅力的に感じられる求人広告や募集要項を考える際の参考になります。
関連記事:「採用基準とは?決め方、見直す項目やポイントと注意点を解説」
採用手法の見直しや他の採用手法を試す
採用計画を見直すと同時に、「これまでと同じ採用手法で問題ないか」も改めて考えることをおすすめします。近年は採用手法が多様化しているため、もしかするとほかの手法を取り入れたほうが、採用活動を効率的に進められるかもしれません。
特に「求人広告を出しても応募がなかなか集まらない」「応募者はいるものの、自社の求める人材像とマッチしない」といった場合は、別の採用手法も検討しましょう。採用手法ごとに、その強みや出会える人材の傾向は異なるため、採用課題が改善する可能性があります。
関連記事:採用手法一覧 中途採用に役立つ採用手法の種類や比較などを総まとめ
採用ブランディングを行う
中途採用を成功に導くには、自社の価値や魅力を転職希望者に伝えて入社意向を醸成する、いわゆる「採用ブランディング」も欠かせません。
売り手市場の現状で中途採用を成功させるには、転職希望者に自社を選んでもらう必要があります。その際、自社の知名度が低いと、なかなか選んでもらえないことも考えられます。
知名度が低い企業でも、転職希望者に「魅力的な企業だ」と感じて選んでもらうには、採用ブランディングが必要なのです。SNSや採用サイトなどを効果的に活用し、独自性のあるコンテンツで自社の魅力を発信しましょう。
労働条件や待遇を改善する
たとえ自社の魅力を発信できていたとしても、労働条件や待遇が転職希望者の希望と合わなければ、応募してもらえない、あるいは辞退される可能性もあります。そのため、給与水準や福利厚生などの条件も適宜見直すと良いでしょう。
また近年は、はたらき方に関する価値観が多様化しているため、リモートワークやフレックスタイム制、時短勤務の導入や副業の解禁も視野に入れることをおすすめします。
採用フローの短縮化や見直し
入社承諾前辞退が課題となっている場合は、転職希望者が応募してから入社するまでのフローを見直して、適宜短縮しましょう。
近年は中途採用の選考期間が短縮化している傾向にあり、一次面接から採用条件通知書の送付までの期間をわずか1~2週間に収めている企業もあるほどです。選考期間が短くなれば、転職希望者が他社に興味を持って自社を辞退するリスクもある程度抑えられます。
また、フローを見直すことで無駄な工数を削減し、採用リソースを最適化できる可能性もあります。そのため、人事・採用担当者のリソース不足が課題となっている場合も採用フローを見直すと良いでしょう。
関連記事:採用フローとは?新卒・中途の違いや運用のポイント、注意点を解説
入社後のフォローを徹底する
「せっかく人材を採用しても、すぐに辞めてしまう」という課題が目立つのであれば、新入社員の入社後フォローである「オンボーディング」を強化しましょう。
オンボーディングとは、組織への定着・戦略化を促すための取り組みのことです。業務スキルの向上を目的とするOJTと異なり、オンボーディングでは「新入社員を組織になじませること」が目的となっています。
オンボーディングの具体的な実施方法は企業により異なりますが、例えば定期的な1on1の実施や、メンターと新入社員の合同研修、新入社員同士で横のつながりをつくるチャットルームの作成などが挙げられます。
外部のサービスを活用する
自社のみで採用活動を行っても中途採用がうまくいかない場合は、外部のサービスを活用しましょう。
例えば、自社の希望条件に合う人材を紹介してもらえる人材紹介サービスや、気になる人材に「攻め」のアプローチを行えるダイレクト・ソーシングサービスなどが挙げられます。また、求人広告サービスを見直して他社に乗り換える、あるいは複数の求人広告サービスに掲載することでも状況が変わる可能性があります。
なお、dodaでは人材紹介サービスとダイレクト・ソーシング、求人広告のいずれもご提案が可能です。適切に活用することで多くの転職希望者にアプローチできます。
難しい課題のある中途採用だからこそ、適切な対策を講じることが大切
今回は、中途採用が「難しい」とされる理由や、課題ごとの解決策を解説しました。
売り手市場が続く中途採用の現場では、転職希望者に自社を選んでもらう工夫が必要です。また、採用した人材を定着させるオンボーディングも欠かせません。
本記事で紹介した内容を参考に、自社の採用フローを見直して改善を目指しましょう。
「対策は講じたものの、中途採用がうまくいかない…」「リソース不足が限界で、対策を試す余裕もない…」とお悩みの人事・採用担当者は、「doda」にご相談ください。貴社の採用計画に最適なサービスを提案し、業界・業種をよく知るキャリアアドバイザーがサポートいたします。
中途採用なら総合支援サービス「doda」
「doda」採用支援サービス一覧

採用コスト削減につながった
doda導入・採用成功事例
おすすめ記事
中途採用が難しい理由と解決策を解説!よくある失敗例も紹介ページです。【中途採用をお考えの法人様へ】dodaサービスのご案内 - 採用成功への扉を開く、総合採用支援サービス