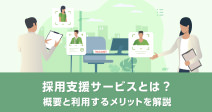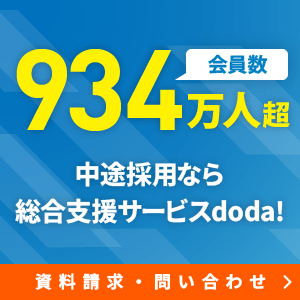2025.10.28
中途採用のキホン
有効求人倍率とは、公共職業安定所(ハローワーク)の有効求人数を有効求職者数で割った数のことです。この数字の大小によって「今、世間では企業にとって人材を採用しやすい状況なのか」を把握できます。
自社の採用活動を進める上での指標としても活用できるため、人事・採用担当者は有効求人倍率を知っておくことが大切です。
そこで本記事では、有効求人倍率の定義や、多くの企業が有効求人倍率を把握している目的などを簡単に解説します。

有効求人倍率とは
有効求人倍率とは、ハローワークに登録して仕事を探している転職希望者の数である“有効求職者数”に対する仕事の数、つまり“有効求人数”の割合です。求人・求職が申し込まれた月を含めて3カ月目までのものを“有効”として扱っています。
有効求人倍率を見ることで、以下のような状況を判断できるようになります。
有効求人倍率の見方
| 有効求人倍率 | どのような状態なのか | 転職希望者・企業にとっての状況 |
|---|---|---|
| 1より小さい | 求職者数に対して求人数が少ない |
・転職希望者にとって、仕事が見つかりにくい ・企業にとって、自社に合う人材を選べる余地がある |
| 1より大きい | 求職者数に対して求人数が多い |
・転職希望者にとって、仕事が見つかりやすい ・企業にとって、自社に合う人材が集まりにくい |
「有効求人倍率が1よりも小さいか否か」によって、採用市場の状態が把握できるのです。このことから、有効求人倍率は人事・採用担当者が意識すべき数字といえます。
なお、有効求人倍率は厚生労働省が毎月調査し、ホームページで公表しています。最新の数値を確認したい方は『一般職業紹介状況(職業安定業務統計)』ページにある『結果の概要』をご覧ください。
有効求人倍率を把握する目的
多くの企業で、人事・採用担当者は以下の目的で有効求人倍率を把握しています。
有効求人倍率を把握する目的
- 1.雇用動向を推し量るため
- 2.景気動向の指標とするため
1.雇用動向を推し量るため
有効求人倍率を基準に、市場全体の雇用の動向を推察できます。そのため、有効求人倍率は採用計画を決める際の指標になります。
例えば、前年の同月と比べて有効求人倍率が下がっている場合は「前年よりも採用しやすい状態になった」といえます。また、厚生労働省の調査結果では業種別・都道府県別の有効求人倍率も発表されているため、他業種と比較した際の現状やエリアごとの傾向も参考になるでしょう。
なお、詳しくは本記事後半で解説しますが、有効求人倍率はあくまでもハローワークでの求人数・求職者数を基に計算されているデータです。そのため、有効求人倍率だけで世間の採用状況を一概に判断できるわけではありません。指標の一つとして活用されることをお勧めします。
2.景気動向の指標とするため
有効求人倍率には、雇用だけでなく景気の動向もある程度反映されます。なぜなら、企業が人材を雇用できる余裕の有無は業績や景気にも左右されるためです。
実際に、この事実を裏付けるデータがあります。
かつて2006年5月には、有効求人倍率は1.08でしたが、2008年9月に起きたリーマンショックの影響で大きく右肩下がりとなり、2009年8月には0.42まで落ち込みました。世界的に不景気な状態に陥ったことによって多くの企業が人材を採用できる余裕がなくなり、転職希望者が就職難に直面したのです。
このように、有効求人倍率には景気も反映されているため、雇用の動向とともに景気を把握する目的でも数値を追うことがあります。
参照元:厚生労働省『平成27年版 労働経済の分析』

有効求人倍率を見る前に知っておきたい用語
有効求人倍率を見る際、専門用語についても把握しておくことで、データをより多角的に捉えられます。ここで、以下の専門用語を確認しましょう。
有効求人倍率を見る前に知っておきたい用語
- 有効求人数
- 有効求職者数
- 新規求人倍率
- 季節調整値
- 完全失業率
有効求人数
有効求人数とは、ハローワークで募集されている求人の数のことです。その月に新規に募集が始まった求人だけでなく、前月から継続している求人も含めて計算されています。
この数値を見ることにより「企業が必要としている労働力はどれぐらいか」がわかります。
有効求人数が多いということはそれだけ企業が多くの労働力を求めており、景気も活発化しているということです。一方で有効求人数が少ない場合は、企業の採用活動が停滞しており、景気が悪化していると判断できます。
有効求職者数
有効求職者数は、ハローワークに登録して、現在仕事を探している人たちの数です。登録から2カ月以内の転職希望者の数を指しています。
有効求職者数を見ると「労働市場の人材供給の状況はどのようになっているのか」がわかります。
有効求職者数が多いということは、転職希望者目線ではライバルが多く、仕事を見つけにくいということです。一方で少ない場合は、多くの方が仕事を見つけられる状況だといえます。
新規求人倍率
新規求人倍率は、その月に仕事を探し始めた新規求職者数に対する、その月に募集を開始された新規求人数の割合です。有効求人倍率と似ていますが「その月に求職・募集を始めた求職者・求人」にのみ限定している点が大きな違いです。
詳しくは以下の表をご覧ください。
有効求人倍率と新規求人倍率の違い
| 有効求人倍率 | 新規求人倍率 | |
|---|---|---|
| 求職者数 | ハローワークに求職者登録を行って2カ月以内の転職希望者の数 | ハローワークでその月に求職者登録を行った転職希望者の数 |
| 求人数 | ハローワークで募集されている求人の数 | ハローワークでその月に募集を開始した求人の数 |
有効求人倍率の中に新規求人倍率が含まれているという形です。なお、新規求人倍率は当月の数字のみを使って算出されるため、有効求人倍率よりもさらに雇用や景気の最新動向が反映されます。
季節調整値
季節調整値は、有効求人倍率の数値から、天候の変化や暦上の休日、企業の決算期などの季節的な変動要因を除いた統計値です。
例えば、観光業の場合は大型連休や年末年始など、特定の時期に繁忙期が訪れるため、季節ごとに求人数や求職者数が大きく変動します。そのため、有効求人倍率だけをそのまま見て分析してしまうと「季節的な要因による一時的な変動なのか、それとも労働市場全体の変動なのか」が不明瞭になる恐れがあります。
そのため、季節的な要因を除外し、より正確な数値を算出する必要があるのです。
完全失業率
完全失業率は、労働力人口のうち仕事に就いていない人の割合のことです。なお労働力人口は「15歳以上のはたらく意欲があり、仕事を探している人々」を指します。
一般的に、有効求人倍率が上昇すると完全失業率が低下する傾向にあります。これは前述の通り、有効求人倍率が高いということはつまり多くの転職希望者にとって仕事を見つけやすい状態であるためです。反対に、有効求人倍率が低下すると、多くの場合完全失業率は上がります。
ただし、有効求人倍率と完全失業率は完全に反比例するわけではありません。なぜなら、有効求人倍率が高くとも求人が特定の業種や地域に偏っていると、仕事を見つけられる転職希望者はごく一部に限られるためです。
そのため、労働市場について正確に把握するには、有効求人倍率と完全失業率の両方を分析する必要があります。
有効求人倍率の計算方法
有効求人倍率は、以下の計算式で算出します。
例えば、有効求人数が460件で有効求職者数が312人の場合、460÷312=1.47…、つまり有効求人倍率は約1.47倍になるということです。これは転職希望者1人当たりおよそ1.47件の仕事があるということなので、転職希望者にとって仕事を見つけやすい状況であることがわかります。
では、有効求人件数230件に対し有効求職者数が425人の場合はいかがでしょうか。230÷425=0.54…となるため、有効求人倍率は約0.54倍、転職希望者1人が就ける仕事が不足しているため、仕事が見つかりにくい状況だといえます。
最新の有効求人倍率の推移
2025年10月現在、厚生労働省のホームページでは8月時点の有効求人倍率が公表されています。
日本国内の有効求人倍率はどのように推移しているのでしょうか。以下の項目別に、数値の推移を確認しましょう。
最新の有効求人倍率の推移
- 業種別の推移
- 地域別の推移
業種別の推移
厚生労働省のデータを基に、2025年8月分の業種別の有効求人倍率、および前年同月比を以下の表にまとめました。
【業種別】有効求人倍率の推移(2025年8月分)
| 業種 | 有効求人倍率 | 対前年同月比 |
|---|---|---|
| 全業種 | 1.09 | -0.04 |
| 管理的職業従事者 | 0.94 | 0.00 |
| 専門的・技術的職業従事者 | 1.76 | -0.10 |
| 事務従事者 | 0.40 | -0.02 |
| 販売従事者 | 1.91 | -0.13 |
| サービス職業従事者 | 2.74 | -0.26 |
| 保安職業従事者 | 6.76 | 0.05 |
| 農林漁業従事者 | 1.04 | -0.07 |
| 生産工程従事者 | 1.49 | -0.03 |
| 輸送・機械運転従事者 | 2.16 | -0.04 |
| 建設・採掘従事者 | 5.10 | -0.03 |
| 運搬・清掃・包装等従事者 | 0.70 | -0.02 |
上記を見るとわかるように、業種全体での有効求人倍率は1.0を超えており、現在は転職希望者にとって仕事が見つかりやすく、企業にとっては自社に合う人材を選びにくい状態となっています。ただし、業種によって有効求人倍率は大きく異なります。保安職業従事者は6.76、建設・採掘従事者は5.10という大きな数値を見せている一方で、事務従事者は10分の1以下の0.40となっているようです。
なお、対前年同月比で見ると全体的に有効求人倍率が若干下がっている一方で、保安職業従事者のみ0.05と増えています。このことは、2025年8月度の保安職業従事者の有効求人倍率が高いことと決して無関係ではないでしょう。
ただし、前年よりも有効求人倍率が下がっている職種であっても、1.0以上マイナスとなっている職種はないため、依然として転職希望者にとって有利な状況であることがうかがえます。
(参照:厚生労働省『参考統計表|一般職業紹介状況(令和7年8月分)について』)
地域別の推移
続いて、厚生労働省が公表しているデータより、地域別の有効求人倍率の推移も見ていきましょう。
【地域別・就業地別】有効求人倍率の推移(2025年8月分)
| 地域 | 有効求人倍率 | 対前年同月比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1.05 | -0.01 |
| 東北 | 1.27 | -0.06 |
| 南関東 | 1.10 | -0.04 |
| 北関東・甲信 | 1.35 | -0.07 |
| 北陸 | 1.54 | 0.01 |
| 東海 | 1.27 | -0.04 |
| 近畿 | 1.10 | -0.03 |
| 中国 | 1.41 | -0.04 |
| 四国 | 1.40 | 0.00 |
| 九州 | 1.16 | -0.09 |
※新規学卒者を除きパートタイムを含む
※季節調整値
地域別の数値では、業種ほど大きな違いはみられません。北陸が1.54とやや高く、北海道は1.05とやや低いですが、いずれにしても2.0よりも大きくなることはなく、また1.0を割ることもないという状況です。
対前年同月比に関しては、北海道が唯一±0で、ほかの地域では全体的に微減しています。こちらに関しては、上述の業種別データと近い傾向がみられます。
(参照:厚生労働省『報道発表資料|一般職業紹介状況(令和7年8月分』)

近年の完全失業率の推移
完全失業率は、総務省統計局のホームページで公表されています。こちらも有効求人倍率と同様に、およそ2カ月前のデータとなっています。
2025年10月時点で公表されている完全失業率の年平均、および季節調整値を含んだ月次の推移は以下の表をご覧ください。
年平均 月次(季節調整値) 2022年 2023年 2024年 2025年5月 6月 7月 8月 完全失業率 2.6% 2.6% 2.5% 2.5% 2.5% 2.3% 2.6%
引用元:総務省統計局『労働力調査(基本集計) 2025年(令和7年)8月分結果』
2025年8月の完全失業率は2.6%で、前月にやや減少したものの結果的に同年5月・6月を上回る数値となっています。なお、2022~24年の年平均は2.5~2.6%となっているため、ここ数年の完全失業率はほぼ横ばいであり、2025年8月の数値も平均から大きく逸脱してはいないと判断できます。
有効求人倍率を見る前に押さえておきたい注意点
有効求人倍率を確認する際は、数値を適切に扱うためにも以下の注意点を念頭に置きましょう。
有効求人倍率を見る前に押さえておきたい注意点
- 注意点1.全ての雇用形態のデータを含んでいる
- 注意点2.ハローワーク以外のデータは含まれていない
注意点1.全ての雇用形態のデータを含んでいる
有効求人倍率は、正規雇用・非正規雇用の区別がないため、全ての雇用形態での求人および転職希望者の数が計算されています。
場合によっては雇用形態ごとに実際の倍率が異なる可能性もありますが、有効求人倍率はあくまでも全ての雇用形態をまとめたものである点に留意してください。
注意点2.ハローワーク以外のデータは含まれていない
世の中にはハローワークに登録せずに採用活動を行っている企業や、仕事を探している転職希望者もいますが、その数は有効求人倍率に含まれていません。
有効求人倍率は、ハローワークに出稿された求人と、ハローワークに登録して仕事を探している転職希望者の数によって計算されたものです。そのため、ハローワーク以外の求人広告媒体などは加味されていない点にも注意しましょう。
ただしハローワークを使っていない企業でも、市場全体の動きを把握するために有効求人倍率を参考にすることは可能です。
有効求人倍率に関連するFAQ
最後に、有効求人倍率に関してよくある質問にお答えします。
有効求人倍率に関連するFAQ
- Q1:有効求人倍率で何がわかりますか?
- Q2:有効求人倍率は高い場合と低い場合、どちらのほうが良いですか?
- Q3:有効求人倍率が1より小さい場合はどうなりますか?
- Q4:有効求人倍率が低い職業は何ですか?
Q1:有効求人倍率で何がわかりますか?
有効求人倍率を見ることで、「転職希望者にとって仕事が見つかりやすい状況なのか」がわかります。また、景気をある程度判断する材料にもなります。
Q2:有効求人倍率は高い場合と低い場合、どちらのほうが良いですか?
企業目線では、有効求人倍率が低いほうが良いといえます。なぜなら、求人数よりも転職希望者数のほうが多い状態となるため、複数の転職希望者からの応募が集まり、企業はより自社に合う人材を選べるためです。ただし、転職希望者にとっては仕事が見つかりにくい状況となります。
反対に転職希望者目線では、有効求人倍率が高いほうが仕事を見つけやすくなるため、良いといえるでしょう。しかし、これは企業にとっては自社に人材が集まりにくい状態となってしまいます。
Q3:有効求人倍率が1より小さい場合はどうなりますか?
有効求人倍率が1.0よりも小さいと、1人の転職希望者が就ける仕事が1つ以下ということになるため、転職希望者目線では好ましくありません。また、「企業が人材を採用する余裕がない」とも判断できるため、景気が悪くなっている可能性もあります。
ただし企業目線では先述の通り、応募が集まるため、自社に合う人材を選べる状況となります。
Q4:有効求人倍率が低い職業は何ですか?
厚生労働省が2025年10月時点で公表しているデータを参照すると、有効求人倍率が1.0を割っている業種は以下の3つです。
有効求人倍率が低い業種(2025年8月時点)
| 業種 | 有効求人倍率 |
|---|---|
| 管理的職業従事者 | 0.94 |
| 事務従事者 | 0.40 |
| 運搬・清掃・包装等従事者 | 0.70 |
※2025年8月のデータ
有効求人倍率を見れば、雇用や景気の動向を推し量れる
有効求人倍率は、市場での雇用の状況や景気の動向を判断する際の指標となるため、採用計画を立てる上でも数値を把握することが非常に重要です。
なお近年は、有効求人倍率が1よりも大きい状態である、売り手市場が続いています。この状況で自社の求める転職希望者を採用するには、戦略的な採用活動が欠かせません。
採用活動を成功させたいなら、「doda」までご相談ください。さまざまな採用サービスの中から、貴社に合うサービスやプランを提案いたします。
採用コスト削減につながった
doda導入・採用成功事例
おすすめ記事
有効求人倍率とは?定義や計算方法、最新の動向をわかりやすく解説ページです。【中途採用をお考えの法人様へ】dodaサービスのご案内 - 採用成功への扉を開く、総合採用支援サービス