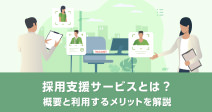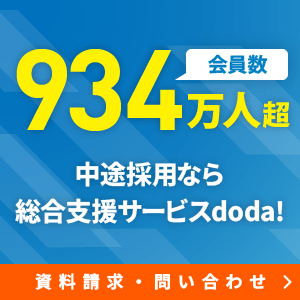2025.10.27
中途採用のキホン
2025年10月現在、労働市場の安定や社会的な課題の解決を目的に、国や自治体によって人材採用に関するさまざまな助成金・補助金の制度が設けられています。人材採用の場では多くの費用がかかるため、組織の持続的な成長にはこれらの制度を活用して費用の削減を図ることが大切です。
本記事で人材採用の助成金・補助金について受給要件を中心に確認し、自社で活用できる制度を押さえましょう。

人材を採用する際に活用できる助成金・補助金とは?
各制度を見ていく前に、本項で「助成金」「補助金」の違いについて説明します。
助成金と補助金は、いずれも返済不要な公的資金を支給する制度のことです。基本的には受給要件を満たした状態で人材採用を行い、その後審査に通過することで費用の一部が補填される仕組みです。
一見似ている2つの制度ですが、「主な管轄」「目的」「審査の難易度」「募集期間」などの部分で異なります。項目ごとに、相違点をまとめました。
人材を採用する際に活用できる助成金と補助金の違い
| 項目 | 助成金 | 補助金 |
|---|---|---|
| 主な管轄 | 厚生労働省 | 経済産業省 |
| 目的 | 雇用促進・労働環境改善・人材育成など | 企業の新規事業・事業拡大など |
| 審査の難易度 | 受給要件を満たせば審査に通過できる可能性が高い | 公募制の場合がほとんどで、ほかの企業との競争の中で採択される必要がある |
| 募集期間 | 通年で募集していることが多い | 募集期間が短いことが多い |
端的にいうと、助成金は従業員の雇用や育成など「人」に対する支援、補助金は、企業が設備投資などに使う「事業」に対する支援という性質の違いがあります。
自社で活用する制度を決める際は、こうした助成金と補助金とで異なる特徴を理解して、検討することが重要となります。
人材を採用する際に活用できる助成金・補助金の例
それでは、人材を採用する際に活用できる助成金・補助金を見ていきましょう。以下に挙げる主要な制度について、受給要件として満たす必要がある主な項目と受給額の目安をご紹介します。
なお、本項でご紹介する内容は制度の大枠であることに加え、制度の見直しにより2025年10月現在から要件が変更されている可能性もあります。詳細は、必ず管轄する公的機関が公表している情報をご確認ください。
人材を採用する際に活用できる助成金・補助金の例
- トライアル雇用助成金
- 特定求職者雇用開発助成金
- 早期再就職支援等助成金
- 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
- 人材確保等支援助成金
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金は、トライアル期間を設けて人材を採用する際に活用できる制度です。早期就職の促進や雇用機会の創出を目的とした制度であり、審査に通過すれば、助成金をもらいつつ、適性やスキルをしっかりと見極めて本採用するかどうかを判断できます。
対象とする人材によっていくつかのコースが用意されており、本項では「一般トライアルコース」の主な受給要件をご紹介します。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の主な受給要件
- 対象者を、ハローワークや民間の職業紹介事業者などからの紹介によって雇い入れること
- 対象者を原則3カ月間、トライアル雇用すること
- トライアル雇用で雇う人材の1週間の所定労働時間を、通常の従業員の1週間の所定労働時間(30時間以上)と同じにすること
なお、トライアル雇用助成金は以降でご紹介する全ての助成金と合わせて「雇用関係助成金」と呼ばれており、共通して次の要件もクリアしなければなりません。
雇用関係助成金共通の主な受給要件
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 支給のための審査に協力すること
- 申請期間内に申請を行うこと
トライアル雇用助成金の審査に通過することで、対象となる人材1人につき、原則として1カ月当たり4万円が支給されます。つまり、トライアル期間の3カ月間雇い続ければ、総額12万円の助成金を受けられます。
(参照:厚生労働省『トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)』)
(参照:厚生労働省『各雇用関係助成金に共通の要件等』)
特定求職者雇用開発助成金
高齢の方や母子家庭の母親、障害をお持ちの方のように、一般的に就職が困難とされる人材の採用を促進するための制度が、特定求職者雇用開発助成金です。本助成金の活用によって、企業は雇用の費用負担を軽減しながら、就労の困難な人材を支援することでCSR(企業の社会的責任)への配慮も行えます。
なお、特定求職者雇用開発助成金にもさまざまなコースがあります。受給要件はそのコースによって一部異なることもありますが、基本的には以下の3つです。
特定求職者雇用開発助成金の主な受給要件
- ハローワークや民間の職業紹介事業者などからの紹介によって雇い入れること
- 雇用保険の一般被保険者として採用すること
- 65歳以上に達するまで継続して雇用し、なおかつ雇用期間が継続して2年以上となることが確実であること
受給額は、コースや企業規模、また雇用の対象となる人材などによって大きく異なります。年度ごとに金額が変わることもあるので、詳しくは厚生労働省の情報を確認してください。
(参照:厚生労働省『雇用関係助成金一覧 4.特定求職者雇用開発助成金』)
早期再就職支援等助成金
中途採用の活性化を目的とする制度が、早期再就職支援等助成金です。
今回は全4コースあるうち、「中途採用拡大コース」「UIJターンコース」の詳細を確認します。
中途採用拡大コース
中途採用拡大コースでは、中途採用の人材がはたらきやすいように雇用管理制度を整備し、その上で雇い入れを拡大した企業に助成金が支給されます。受給要件の大枠は、以下の通りです。
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)の主な受給要件
- 「中途採用によって雇い入れられている」「期間の定めなく雇い入れられている」などの一定の条件を満たした人材を雇用すること
- 中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること
- 中途採用計画の期間に、対象者を2人以上雇い入れること
- 中途採用計画の期間に、過去3年間と比べて中途採用率を20ポイント以上上昇させることなど
受給要件を満たすことで原則として50万円が、特に45歳以上の中途採用率の拡大を実現した場合には100万円が助成されます。
(参照:厚生労働省『早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)』)
UIJターンコース
地方創生を促進するために、東京圏からの移住者の雇い入れを行う企業をサポートする目的で創設されたものがUIJターンコースです。以下の要件を満たすことで、採用活動で東京に出向く際の交通費や宿泊費といった経費の一部が助成されます。
早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)の主な受給要件
- 採用活動に係わる計画書を管轄の労働局に提出し、労働局長から認定を受けること
- 計画書に定めた期間に、採用パンフレットや自社ホームページの作成・就職説明会の実施・外部専門家への相談といった採用活動を行うこと
- 「東京圏からの移住者である」「継続した雇用が確実である」など支給対象となる人材を雇用すること
審査に通過することで、100万円を上限として、助成の対象となる経費の合計額に中小企業であれば1/2、それ以外の場合は1/3の助成率を乗じた額を受け取れます。
(参照:厚生労働省『早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)』)
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)は、雇用機会が特に不足している地域に事業所を持つ企業を対象とした制度です。その地域に居住する人材を雇い入れるために、事業所の設置・整備を行うことで、1年で最大3回にわたって助成金が支給されます。
受給要件は1回目と2・3回目で異なり、1回目では以下の条件を全て満たさなければなりません。
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)1回目の主な受給要件
- 本助成金の対象となる地域(同意雇用開発促進地域等)に事業所が所在すること
- 事業所の施設・設備の設置や整備、および地域に居住する人材の雇い入れに関する計画書を労働局に提出すること
- 計画期間内に事業所の用に供する施設や設備を行うこと
- 計画期間内に雇用すること
- 地域に居住する人材で、常時雇用する雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者を、計画期間内にハローワークなどの紹介によって3人以上雇い入れること
- 事業所の被保険者数を、計画の前日から3人以上増加させること
本助成金の受給額は、企業規模や事業所の設置・整備にかかった費用、雇用した対象となる人材の数や受給の回数に応じて決まります。例えば、中小企業の事業所で、整備に300万円かけて3人の雇用に成功した場合には75万円が助成されます。
(参照:厚生労働省『地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)』)
人材確保等支援助成金
労働環境の向上を図り、魅力あふれる職場をつくる企業をサポートする制度が人材確保等支援助成金です。全部で7コースが設けられていますが、ここではその中でも業種を問わずに活用しやすい「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」を紹介します。
本コースでは、雇用管理制度や業務負担の軽減を図る機器の導入により、離職率の低下に取り組んだ際に助成金が支給されます。具体的な受給要件は、以下の通りです。
人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)の主な受給要件
- 雇用管理制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること
- 計画の実施機関内に、雇用管理制度または業務負担軽減機器を導入すること
- 雇用管理制度等整備計画の期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、当該計画を提出する前の1年間よりも1ポイント以上低下させること
助成金の受給額の決まり方は、雇用管理制度と機器のどちらを導入して要件をクリアしたかによって異なります。
雇用管理制度の場合には、「賃金規定制度」「諸手当等制度」など、細分化された制度の種類ごとに受給額が決まっています。例として、賃金規定制度の導入では、原則40万円が受給額です。
対して機器では、上限を150万円として、その導入に際してかかった経費のうち1/2の金額を受給できます。
(参照:厚生労働省『人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)』)

障害をお持ちの方を雇用する際に活用できる助成金・補助金の例
本項では、障害をお持ちの方を雇用する際に活用できる助成金・補助金に焦点を当ててご紹介します。
障害をお持ちの方の雇用を推進することは、自社に合った人材と出会える可能性が広がる上に、多様性のある企業文化の醸成にもつながります。以下の助成金・補助金を活用し、障害をお持ちの方がはたらきやすい環境を整備して、組織力の向上を図りましょう。
障害をお持ちの方を雇用する際に活用できる助成金・補助金の例
- 障害者介助等助成金
- 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
- トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
- 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
障害者介助等助成金
障害者介助等助成金は、障害をお持ちの方を継続して雇用するために介助者の配置・委嘱などの措置を取る企業を支援する制度です。措置の方法によって4種類に分けられ、それぞれで要件が設けられていますが、以下の部分は共通しています。
障害者介助等助成金の主な受給要件
- 本助成金の対象となる障害をお持ちの方を継続して雇用すること
- 本助成金で定められている措置を実施しなければ、当該人材の雇用継続が困難であると認められること
- 障害者雇用納付金制度助成金の不支給措置が取られていないこと
- 不正受給で返還金が生じている場合、返還が終了していること
障害者介助等助成金は種類ごとに受給額の算出方法が大きく異なるので、詳しくは厚生労働省のWebサイトに掲載されている情報を確認してください。
(参照:厚生労働省『障害者介助等助成金』)
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度の障害をお持ちの方を複数人継続して雇用している企業に支給される助成金が、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金です。
具体的に雇用の対象となる人材は、重度身体障害・知的障害・精神障害をお持ちの方々です。これらの方たちを複数人安定して雇用できると認められる企業で、雇用継続のために必要な施設や設備を設置・整備する場合に、費用の一部が補填されます。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の主な受給要件
- 対象となる人材を10人以上継続して雇用していること
- 在籍する従業員のうち、その2割以上が対象となる人材であること
- 経済基盤および雇用条件が著しく良好であると認められること
- 重度障害をお持ちの方の雇用を推進するにあたって規範になると認められること
- 対象となる人材を雇用するために必要な施設や設備を設置・整備すること
- 過去に助成金を受けて障害をお持ちの方を採用した際に、その方が自己都合以外の理由で離職していないこと
- 過去に助成金を受けて採用した障害をお持ちの方が自己都合で離職した際、代替雇用をしていること
受給要件は厳格ですが、審査に通過できれば、5,000万円を限度に施設や設備の設置・整備費用の2/3に当たる金額の助成を受けられます。
(参照:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構『重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金』)
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
前述で紹介したトライアル雇用助成金の中には、障害をお持ちの方を対象とした「障害者トライアルコース」があります。企業と障害をお持ちの方が互いに理解を深め合える場を制度として設けて、雇用機会を創出することを目的としています。
これまで障害をお持ちの方を採用した事例がない場合には、本助成金をきっかけに雇用体制を整えてみてはいかがでしょうか。
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)の主な受給要件
- ハローワークや民間の職業紹介事業者などからの紹介によって雇い入れること
- トライアル雇用の期間中に、雇用保険被保険者資格取得の届け出を労働局に行うこと
- 継続雇用を希望している人材を対象とすること
- 障害者トライアル雇用制度を理解した上で継続した雇い入れを希望する人材を対象とすること
- 障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、一定の要件を満たす人材を対象とすること
受給要件を満たした場合には、対象となる人材1人につき、原則として月額最大4万円を最長で3カ月間受け取れます。
(参照:厚生労働省『障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース』)
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
一般的に就職が困難な人材の雇用促進を目的とする特定求職者雇用開発助成金でも、障害をお持ちの方の雇用を対象としたコースが設けられています。そのうち、「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」は、障害者手帳を有していない発達障害や難病をお持ちの方を対象とした制度です。
これらの方の雇用に際し、特定求職者雇用開発助成金の項目でも紹介した以下の受給要件を満たすことで助成を受けられます。
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の主な受給要件
- ハローワークや民間の職業紹介事業者などからの紹介によって雇い入れること
- 雇用保険の一般被保険者として採用すること
- 65歳以上に達するまで継続して雇用し、なおかつ雇用期間が継続して2年以上となることが確実であること
受給額は企業規模で異なり、中小企業の場合は2年をかけて120万円が、それ以外の企業には1年をかけて50万円が原則として支払われます。
(参照:厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)』)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
特定求職者雇用開発助成金のうち、「特定就職困難者コース」も障害をお持ちの方の雇用に対して助成金が支給されます。審査に通過することで、原則として以下の金額を受け取れます。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の受給額
| 対象 | 受給額 | 助成対象期間 |
|---|---|---|
|
・身体障害 ・知的障害 |
120万円(中小企業以外の場合は50万円) | 2年(中小企業以外の場合は1年) |
|
・精神障害 ・障害の程度が重度 ・障害をお持ちで、45歳以上の方 |
240万円(中小企業以外の場合は100万円) | 3年(中小企業以外の場合は1年6カ月) |
身体障害や知的障害の場合でも、障害の程度が重度に該当する、あるいは45歳以上の障害をお持ちの方の雇用では下段の受給額が適用されます。
(参照:厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)』)
採用時に活用できる助成金・補助金の申請方法
上記でご紹介した助成金を申請するためには、まず、管轄のハローワークに審査の必要書類を指定の期間内に提出する必要があります。申請方法は、助成金申請窓口に直接出向くか、または「雇用関係助成金ポータル」からオンライン上で申請するかの2通りから選べます。
各助成金で必要となる書類が異なるため、厚生労働省のWebサイトで情報を事前に確認し、不明点がある場合には労働局やハローワークの窓口で問い合わせましょう。
人材採用に関連する助成金・補助金を活用する際に注意したいこと
最後に、人材採用で助成金・補助金を活用する際に注意が必要なポイントをご紹介します。
人材採用に関連する助成金・補助金を活用する際に注意したいこと
- 注意点1.各助成金・補助金で異なる要件が設けられている
- 注意点2.助成金・補助金制度が見直されることがある
注意点1.各助成金・補助金で異なる要件が設けられている
助成金・補助金は、その種類によって異なる受給要件が設けられていることを念頭に置いておきましょう。たとえ同じ制度内の助成金・補助金であっても、細分化されたコースの中で違う要件が設定されている場合もあります。
万が一、要件を見落としてしまうと、受給が認められないこともあるため注意が必要です。
各制度の要件の情報はインターネット上で数多く出てきますが、中には抜け漏れや誤りがあるかもしれないので、必ず管轄する公的機関の情報を基に行動することが大切です。
注意点2.助成金・補助金制度が見直されることがある
助成金・補助金の詳細を調べる際は、それが最新の情報であることの確認も忘れてはなりません。助成金・補助金の制度は頻繁に見直されているため、それに伴い要件や必要書類なども変わっている可能性があります。
サイト内の情報が最新のものであるという確証が得られない場合には、労働局やハローワークなどの窓口に問い合わせると間違いがないでしょう。
人材採用では費用負担の軽減を図れる助成金・補助金の制度が数多くある
人材採用では、トライアル雇用助成金や特定求職者雇用開発助成金、また早期再就職支援等助成金など、さまざまな助成金・補助金を受給できる可能性があります。
各制度の受給要件を確認した上で、自社に該当する制度が見つかれば積極的に活用し、人材採用の費用負担を軽減しましょう。
なお、費用を抑えた人材採用を推進するためには、ぜひ「doda」にご相談ください。経験豊富な専任の担当者が、貴社に適した助成金・補助金の制度とともに、費用の軽減を図れる採用戦略をご提案いたします。
採用コスト削減につながった
doda導入・採用成功事例
おすすめ記事
人材を採用する際に活用できる助成金・補助金の一覧と申請方法を解説ページです。【中途採用をお考えの法人様へ】dodaサービスのご案内 - 採用成功への扉を開く、総合採用支援サービス