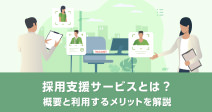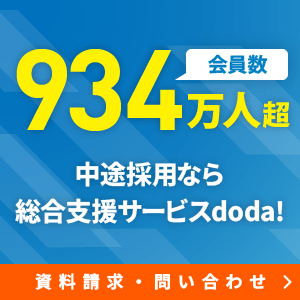2025.05.02
中途採用のキホン
少子高齢化が進む近年、人材の採用はますます難しくなっています。採用活動をしているものの人材が集まらない、あるいは採用しても早期に離職してしまう…といった課題に直面している企業も少なくありません。こうした課題を解決するには、「母集団形成」が重要です。
今回は母集団形成の概要を、方法や効果を上げるためのポイントとともに解説します。「より効果的な採用活動を実施したい」とお考えであれば、ぜひ最後までご覧ください。

母集団形成とは
母集団形成とは、自社の求人に興味を示す転職希望者を集めることを指します。
母集団形成では自社に関心を寄せている人材を幅広く捉えて、取りこぼすことなく集める必要があります。ただし、ここで注意していただきたいのは、とにかく人数を集めれば良いわけではない、ということです。
母集団にいくら多くの人数が集まっても、その中に自社が求める人材がいなければ、採用活動の目的は果たせません。母集団形成を実施する際は、集める人数だけでなく、人材の「質」にもこだわることが求められるのです。
母集団形成を実施するメリット
適切な母集団形成は、企業の採用活動に多くの利益をもたらす可能性があります。ここでは、企業が母集団形成を実施する4つのメリットを解説します。
メリット①採用活動を計画的に進められる
母集団形成を実施するメリットとして、採用活動の進捗を明確にして、計画的に選考を進められることが挙げられます。
母集団形成を実施する際には、過去の採用実績を参考にしながら、各選考ステップを通過する人材の割合を想定し、KPI(重要業績評価指標)の目標値を設定します。例えば、最終的に10人を採用したい場合、2次選考では20人、1次選考では50人…といった具合に、各フェーズでの目標人数を逆算して決めるのが一般的です。
そのため、特定のプロセスで目標人数に達しなかった場合、採用人数の達成が困難だということが即座にわかります。これにより早い段階で立て直しを図れるため、「目標の採用人数に届かなかった」というリスクを軽減することが期待できます。
メリット②採用にかかる費用の適正化を図れる
母集団形成は、採用にかかる費用の適正化にもつながります。
十分な母集団が確立できていない状態で採用活動を進めてしまうと、目標の採用人数を達成できないリスクが高まります。その結果、2次募集や3次募集が必要となり採用活動は長期化してしまい、採用にかかる費用も増えるでしょう。
一方、母集団形成を適切に実施できている場合には、計画的に採用活動が進められるため、長期化を抑制し、費用の適正化を図れます。
メリット③入社後のミスマッチを低減できる
応募数を増やすだけでなく、入社後のミスマッチの予防につながる点も母集団形成のメリットの一つです。
母集団形成を実施するに当たっては、「自社が求める人材像」を明確にするところから始まります。これにより社内の採用基準が定まり、求める人材像の認識を擦り合わせることができるため、一貫性のある採用が可能となります。
もし、こうした事前準備をせずに採用活動を始めると、自社に必要な人材のイメージが社内で共有できず、社風に合わない人材を採用してしまうかもしれません。そうなれば、早期離職を招き、採用や育成にかかった費用が無駄になってしまうため、企業としては大きな損失につながるでしょう。
母集団形成の段階から自社に合った人材を具体化できていれば、こうしたミスマッチのリスクを減らし、効率的な採用活動を実施できる可能性が高まります。
メリット④事業成長に直結する可能性がある
母集団形成は、将来的な事業の成長につながることも期待できます。
質の高い母集団形成を安定的に実施できれば、自社に合った人材を継続的に採用できるようになる可能性が高まります。これにより、自社に必要なスキルや経験を持つ人材が社内に増えていき、継続的な事業成長につながるでしょう。
また、母集団形成自体のノウハウを蓄積していくことで、社会情勢による転職市場の変化にも柔軟に対応できる採用体制を構築できるようになるかもしれません。
母集団形成が重要視されるようになった背景
ここからは、採用活動で母集団形成が重要視されるようになった3つの背景を解説していきます。背景に対する理解を深め、より効果的な採用戦略を立てるためのヒントを見つけてください。
「売り手市場」による人材の採用競争の激化
母集団形成が注目されるようになった大きな理由として、人手不足による人材の採用競争の激化が挙げられます。
日本では、深刻な少子高齢化の影響を受けて、生産年齢人口(15歳以上65歳未満の生産活動の中心となる人口層)が年々減少しています。総務省のデータによると、日本の生産年齢人口は、1995年の約8,716万人をピークに減少を続け、2024年には約7,373万人まで減りました。
こうした状況により、各業界で人手不足が深刻化しており、多くの企業が人材の採用に力を入れています。このような売り手市場の中で、自社が求める人材を効率的に採用するために、母集団形成が重要なのです。
(参照:総務省『生産年齢人口の減少』)
(参照:総務省統計局『人口推計(2024年(令和6年)10月確定値、2025年(令和7年)3月概算値)』)
転職市場の活性化
転職市場が活性化していることも、母集団形成が重要視されるようになった理由の一つです。
近年、多様な働き方が広く受け入れられるようになり、転職もキャリアアップのための一般的な選択肢として考えられています。これにより、転職希望者からの応募を得やすくなった一方で、入社後にミスマッチが生じた場合に、早期に離職して別の企業に転職してしまう可能性も高まりました。
そのため、適切な母集団形成によって、自社とのマッチ度の高い人材を集めることが求められています。
戦略的採用への転換
戦略的な採用活動が企業に求められるようになったことも、母集団形成が注目されている理由の一つに考えられます。
ここまで見てきたように、現在は売り手市場で応募が集まりづらくなっているばかりか、離職のハードルが下がっています。こうした状況下で、やみくもに採用活動を進めても自社に合った人材からの応募はなかなか集まりません。企業には、事業や経営の方針ともひもづいた戦略的な採用活動の実施が求められています。
そこで、計画的に、かつ費用の適正化を図りながら採用活動を進められる手法として、母集団形成が注目を集めているのです。
中途採用の母集団形成の採用手法
中途採用の場合、母集団形成の方法として以下が挙げられます。
中途採用の母集団形成の採用手法
- 人材紹介サービス
- 求人広告
- ダイレクト・ソーシング
- 合同企業説明会をはじめとする転職希望者向けのイベント
- リファラル採用
- SNS
それでは順に詳細を確認していきましょう。
人材紹介サービス
人材紹介サービスとは、企業が提示した採用条件に基づき、担当者から人材の紹介を受けられるサービスのことです。採用条件を細かく設定できるため、採用したい人材像が明確になっている場合の母集団形成に向いています。
人材紹介サービスを活用するメリットとしては、自社に合った人材を見つけやすいことが挙げられます。業界や業種に精通した担当者が、採用条件に合った人材を紹介してくれるため、入社後の活躍が期待できるのはもちろん、早期離職のリスクも軽減することができるでしょう。特に専門職の採用のように、採用条件とのマッチ度が重視される場合には役立ちます。
ただし、人材紹介サービスでは入社者年収の3割程度を紹介手数料として支払う必要があり、ほかの方法よりも費用が高い傾向にあります。
求人広告
求人広告を出すことも、母集団形成を進める一つの手法です。
求人広告は、多くの転職希望者が「まずは情報収集として見ておこう」と目を通すため、母集団の人数を集めやすいという特徴があります。
しかし、求人広告は広く公開されるため、自社には適さない人材からの応募が集まることもあるでしょう。その分、選定および選考に手間がかかることはある程度避けられないといえます。
ダイレクト・ソーシング
ダイレクト・ソーシングは、企業が転職希望者へ直接アプローチする採用手法です。人材紹介サービスなどに登録された人材データベースから、自社の求める条件に合う転職希望者を選んで連絡を取り、選考へとつなげていきます。
ダイレクト・ソーシングでは、自社からの連絡に対して何らかの反応があった転職希望者を母集団に含めます。自社が求める条件を満たした人材だけにアプローチできるため、質の高い母集団形成が可能です。
その反面、企業が主体となって候補者を探し、アプローチする必要があるため、人事・採用担当者に発生する工数は多くなります。大量採用を検討している場合には、不向きな手法といえるでしょう。
合同企業説明会をはじめとする転職希望者向けのイベント
合同企業説明会や転職フェアなど、複数の企業が集まる転職希望者向けのイベントに出展することも母集団形成を実施する上で有効な採用手法です。
このようなイベントでは、プレゼンテーションやパンフレットの配布を通して自社の魅力を直接アピールできます。また、参加者の中には他社を目的に訪れた転職希望者も多く、そうした人材に対して偶発的に自社の存在を知ってもらえる点も、大きなメリットといえるでしょう。
しかし、短時間で複数の転職希望者を相手する必要があるため、その場で一人ひとりと綿密なコミュニケーションを取るのは難しい傾向にあります。
リファラル採用
社員から知人を紹介してもらい、選考へとつなげる採用手法をリファラル採用といいます。リファラル採用では、選考を受ける人材が、社員を通じて自社の雰囲気や仕事内容を事前に把握できているため、入社後のミスマッチが起きるリスクが少ない傾向にあります。また、紹介してくれた社員に一定のインセンティブを支払うケースが一般的ですが、ほかの採用手法と比べると採用にかかる費用が抑えられるのも利点です。
なお、リファラル採用は質を重視する採用手法であり、人数を集めることは難しいため、母集団形成の観点から考えると、ほかの採用手法と併用したほうが良いでしょう。
SNS
X・Instagram・YouTubeといったSNSも、母集団形成で活用できます。
SNSは無料または低価格で利用できるものが多いため、採用に関する情報発信にかかる費用を抑えられる点がメリットです。また、幅広い層に情報を届けられるため、転職希望者だけでなく、まだ転職活動を始めていない潜在層も含めてアプローチできます。
ただし、SNSによる採用活動で成果を出すためには、一定のノウハウと中長期的な取り組みが必要となります。また投稿した内容によっては、企業のイメージを下げてしまうリスクもあるので注意が必要です。
採用活動でSNSを使用するには、人事・採用担当者に専門のスキルが必要であるといえます。
母集団形成の手順
母集団形成は、次の4つの手順に沿って進められるのが一般的です。
母集団形成の手順
- 採用計画を立てる
- 母集団形成の採用手法を決める
- 採用活動を始める
- 課題を洗い出して改善する
各手順の実施時に気をつけるべきポイントとともに、詳細を確認していきましょう。
ステップ①採用計画を立てる
母集団形成を始めるに当たって、まずは採用の計画を立てていきます。このとき検討しなくてはならないものとして、「採用の目的」「採用したい人材の条件」「採用予定人数」「KPIの目標値」「採用スケジュール」の5つがあります。
採用の目的
効率的な母集団形成を行うためには、自社の人材採用の目的を明確に決めておく必要があります。
目的を決める際は、「欠員を補充するため」「今後の成長のため」などのように抽象的に捉えるのではなく、より具体的に内容を検討することが大切です。例えば、「3年以内に自社内のDX推進を図るため、今年度中にITスキルを持った人材を5人採用する」といったイメージです。
目標を明確にすることで、採用活動の方向性が定まり、採用したい人材の条件の設定や採用手法の選定もスムーズに決められるようになるでしょう。
採用したい人材の条件
採用の目的が決まれば、その内容に沿って採用したい人材の条件を精査していきます。条件を明確化し、社内で共有できるかたちに整えることで、母集団形成の精度と効率を高められます。
採用したい人材の条件の決め方として挙げられるのは、以下の2通りです。
採用したい人材の条件の決め方
- 演繹(えんえき)的アプローチ:今後の展望から逆算して定義する
- 帰納的アプローチ:既に活躍している人材から定義する
いずれかの手法を用いて、人材の条件が決まれば、最後に現場からの意見もヒアリングしましょう。経営者や人事・採用担当者の視点だけでなく、現場のニーズを反映させることで、ミスマッチのリスクをより抑えられる母集団形成につながります。
採用予定人数
採用計画の策定にあたり、採用予定人数を決めておくことも欠かせません。次の4つの観点から、採用予定人数を総合的に判断しましょう。
採用予定人数の判断材料
- 事業計画
- 現在の人員の構成
- 経営者や人事目線のニーズ
- 現場のニーズ
母集団の数は採用予定人数から逆算して決めることになるため、上記の判断材料に基づきしっかりと精査して必要な人員数を算出したいところです。
KPIの目標値
採用予定人数と過去の採用実績を参考にして、KPIの目標値を決めます。決め方としては、採用人数から各選考プロセスの通過率を想定し、最終的に必要となる母集団の規模を設定していくのが一般的です。
母集団が大き過ぎる場合、選考に時間や費用がかかるだけでなく、ミスマッチが起きる可能性も高まります。反対に母集団が小さすぎると、入社承諾前辞退が1件出るだけでも採用目標に届かなくなってしまうかもしれません。
KPIの目標値の設定は、円滑な採用活動の実施に向けて特に重要になるポイントのため、慎重に決めましょう。
採用スケジュール
採用スケジュールは、入社のタイミングから逆算して決定します。採用の目的を踏まえ、いつまでに採用しなければならないのかを明確にしましょう。
選考に当たっては面接官との日程調整や、関係部署との連携が必要となる場合もあるため、余裕を持ったスケジューリングが求められます。
ステップ②母集団形成の採用手法を決める
採用の計画が決まったら、それに基づいて母集団形成を実施する際の採用手法を検討します。採用手法の選定時に考えるべき項目は、以下の通りです。
採用手法を決める際に検討すべき項目
- 採用にかかる費用は予算内に収まるか
- 自社に合った人材にアプローチできるのか
- 現状の人員で運用可能か
- スケジュール通りに進行できるか
前項で説明した通り、採用手法には人材紹介サービスや求人広告、ダイレクト・ソーシングなどさまざまな種類があります。母集団の全てを一つの手法で集める必要はないため、上記の項目を参考にしながら、いくつか手法を選択して実施すると良いでしょう。
ステップ③採用活動を始める
選択した手法ごとに、採用活動を進めていきます。特に意識すべきなのは、採用活動を通して自社の魅力をアピールし、転職希望者に興味・関心を持ってもらうことです。
例えば、「当社の自慢は社内コミュニケーションが活発な点です」とアピールしているのにもかかわらず、採用活動を事務的・形式的に進めると魅力は伝わりきらないでしょう。それどころか転職希望者に、「実態と違うのでは?」と不信感を与えてしまう可能性があります。
このように自社の魅力を十分に伝えきれない採用活動は、円滑な母集団形成の妨げになってしまうかもしれません。採用活動を通して、現場の雰囲気やキャリアパスなど、「入社後にどのように働けるのか」が伝わるような情報発信を意識しましょう。
ステップ④課題を洗い出して改善する
採用活動は、「人」を対象とするため、必ずしもスケジュール通りに進むとは限りません。そのため採用活動の実施中は、定めてきた各目標に基づき、進捗の管理および課題の洗い出しを行い、定期的な見直しを図りましょう。
また、今後の採用活動のために、数値としてわかるデータを蓄積しておくことも重要です。以下に挙げるデータは、特に算出して保存しておきたいところです。
採用活動で蓄積しておくべき主なデータ
- 採用手法ごとの応募数
- 選考過程ごとの通過人数
- 選考合格者数
- 発生した費用
これらのデータを分析することで、どの取り組みが効果があり、どのプロセスに改善が必要なのかを把握でき、今後の採用活動の効率化につながります。
母集団形成を成功させるコツ
母集団形成を成功させ、計画的な採用活動を実現するためには、次の3つのポイントを意識しましょう。
母集団形成を成功させるコツ
- 求めるスキル・経験を明確にする
- 配属先の部門から協力を得る
- 自社の方針に一貫性を持たせる
詳細を順に解説します。
求めるスキル・経験を明確にする
母集団形成を実施する際には、スキルや経験など、人材に求める条件をできる限り具体的にすることが大切です。
中途採用では、新卒採用のように入社後の育成を前提とするのではなく、即戦力としての活躍を期待して採用します。そのため、母集団形成では人材に求める条件をきちんと精査して、明確にしておくことが重要なのです。
人材に求める条件を明言することで、母集団に集まる人材が絞られ、採用後に「想定した人材でなかった」となるリスクを減らせるでしょう。
配属先の部門から協力を得る
母集団形成を成功させるためには、配属先との連携も図りつつ進めていくことも欠かせません。
人事部門だけで母集団形成を実施すると、採用したい人材に関する認識について、配属予定の部門との間にずれが生じてしまう恐れがあります。それが原因で、人材の早期離職を招いてしまうことも考えられます。
母集団形成を実施する際には、人材に求める条件や採用予定人数はもちろん、採用スケジュールや採用手法まで、配属先の部門とコミュニケーションを取りながら決めましょう。
自社の方針に一貫性を持たせる
母集団形成は自社内で一貫した考えや価値観に基づいて、進めていくことも成功のためのポイントです。
方針があいまいな状態では、人事・採用担当者間での認識のずれを招き、効果的な母集団形成には至らないかもしれません。その結果、求める条件とはかけ離れた転職希望者からの応募が増え、その対処のために不要な工数が発生してしまう恐れがあります。
こうした事態を防ぐためにも、母集団形成を実施するには、社内で綿密に認識を擦り合わせておくことが重要です。また、採用方針は一度決めたら終わりではなく、定期的に見直しを行い、その内容をきちんと共有することも欠かせません。
母集団形成の課題と解決策
ここでは、母集団形成時に想定される課題と解決策を解説します。事前に注意すべきポイントを確認し、母集団形成を円滑に進めましょう。
課題①求人情報が認知されていない
母集団形成時に起こり得る課題として、求人情報がなかなか認知されず転職希望者を集められないケースが考えられます。これは、転職希望者が情報収集している段階で、自社の求人情報にそもそも気づけていないことが主な原因です。
このように認知度が不十分な状況を解決するためには、求人情報の露出方法を見直す必要があります。特にオンラインによる一方的なアプローチに限定していた場合は、より直接的に双方向のコミュニケーションが取れる手法を取り入れてみると良いでしょう。
具体的には、合同企業説明会やSNSを使用した採用活動などが挙げられます。これにより、転職希望者と直接つながる点を増やし、地道ではあるものの着実に認知度を向上させることが見込めます。
課題②認知はされているが魅力が伝わっていない
母集団形成で直面する課題として、転職希望者に求人情報を認知されているにもかかわらず、魅力が十分に伝えられていないケースもあります。掲載している求人情報では、転職希望者に自社の魅力を訴求しきれておらず、応募につながっていないのです。
このケースでは、掲載する求人情報の内容や表現を見直すことが求められます。見直す際は、転職希望者の目線に立つことを意識して、転職者に具体的なイメージを持ってもらえるような内容に仕上げましょう。
課題③採用したい人材からの応募が集まらない
母集団として十分な人数がそろっていたとしても、採用したい人材からの応募が集まらないということも起こり得ます。この中から仮に人材を採用しても、マッチ度が低く早期離職につながりかねません。
採用したい人材から応募が集まらない原因としては、転職希望者に対して自社が求める人材像を明確に伝えきれていないことが挙げられます。
そのため、まずは採用条件や求めるスキル、人物像などを社内で明確に定義し、人事・採用担当者間で共有することが重要です。その上で、求人情報・採用広報・選考プロセスといった全ての接点で、一貫性のあるメッセージを発信することが求められます。
母集団形成の強化を実現した事例
最後に、母集団形成によって効果的な採用活動を実現した事例を紹介します。
事例①株式会社山貴建設
損害保険事故復旧工事を専門とする株式会社山貴建設では、事業拡大を見据えて、工事現場のマネジメントを行うディレクター職の採用を強化していました。しかし、建設業の転職市場では競合が多く、十分な母集団形成ができなかったとのことです。
そこで同社では、待ちの採用手法だけでなく、自社の魅力を積極的に伝えるべく、ダイレクト・ソーシングサービスの『doda ダイレクト』を導入しました。
導入後は、まず採用の計画を決めるところから始まります。dodaの専任の担当者との話し合いを重ねて、求める人材像や自社のアピールポイントを明確に決めていきました。
こうした対応によって、導入から2カ月経ったころから面接も増え、結果的に6人との面接を実施して1人の採用が決まったそうです。
事例記事:競合の多い建設業界で採用を実現。求人広告&ダイレクト・ソーシング併用による母集団形成と「面接1回の選考早期化」
母集団形成は採用活動の効率化やミスマッチの防止につながる
今回は母集団形成の概要を、採用手法や効果を上げるためのポイントとともに解説しました。
母集団形成とは、自社の求人に興味を示す転職希望者を集めることを指します。適切に実施することで、採用活動の効率化やミスマッチによる早期離職の防止につながります。
人材紹介サービスや求人広告、ダイレクト・ソーシングなどさまざまな採用手法の中から自社に合ったものを選び、母集団形成を実施しましょう。
複数の採用手法を組み合わせて、より効果的な母集団形成を図りたいとお考えであれば『doda』の各サービスの利用をご検討ください。本記事で解説した採用手法を複数提供しており、採用ニーズにワンストップ・ワンブランドで対応いたします。

採用工数削減につながった
doda導入・採用成功事例
おすすめ記事
母集団形成とは?採用手法と手順、課題ごとの解決策を解説ページです。【中途採用をお考えの法人様へ】dodaサービスのご案内 - 採用成功への扉を開く、総合採用支援サービス