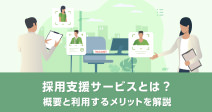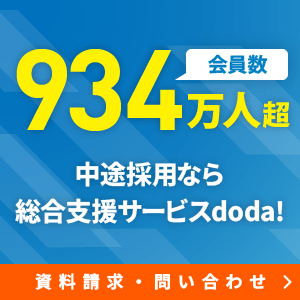2025.08.29
中途採用のキホン
採用代行について調べている中で、「採用代行は違法の可能性がある」という情報を見聞きした経験がある人事・採用担当者もいるでしょう。多くの企業が利用しているはずの採用代行が、違法行為になることなどあるのでしょうか?
そこで今回は、採用代行が違法になる可能性の有無や、利用する前に把握しておきたい法律などを解説します。懸念点を払拭した上で採用代行を利用したいとお考えなら、ぜひご一読ください。

採用代行(RPO)とは?
採用代行が違法かどうかについて言及する前に、その定義を確認しておきましょう。
採用代行とは、採用業務を企業に代わって実施するサービスのことです。
採用計画の立案や母集団形成、応募があった転職希望者への対応など、採用業務の一部、あるいは全てを代行してくれます。利用することにより、採用業務の負担を軽減できるだけではなく、採用活動そのものの品質向上も見込めます。
関連記事:RPO(採用代行)とは?業務範囲やメリット、費用相場を解説
採用代行(RPO)は委託募集に該当するサービス
採用代行は、一定の条件に合致する場合「委託募集」に該当します。この委託募集とは、厚生労働省によって定められた労働者を募集する際の区分の一つで、以下の通り定義されるものです。
「委託募集」とは、「労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして労働者の募集に従事させる形態で行われる労働者募集」を言います。
(引用:厚生労働省『委託募集について』)
ただし、全ての採用代行が上記の定義に該当するわけではありません。
採用代行で募集や選考などの採用活動の業務を委託する場合は、「委託募集」に該当します。一方で、募集や選考は自社で行い、採用戦略の立案や試験問題の作成などの業務を外注する場合は、委託募集には当たりません。委託する業務の内容次第で委託募集に該当しないケースもあるため、採用代行の利用時には留意しておきましょう。
また、特定の職種やポストで転職希望者を集めて企業にあっせんする転職エージェントなども、委託募集ではなく職業紹介に分類されるため、そもそも委託募集には該当しません。
委託募集は基本的には許可が必要
報酬が発生する委託募集を実施する場合は、委託者(業務を委託する企業)と受託者(業務を代行する会社)の双方が、厚生労働大臣あるいは都道府県労働局長から許可等を取得しなくてはならない、と職業安定法で定められています。
採用代行の利用時にも、当然この点を順守しなくてはなりません。
なお、上記の許可を得るためには、職業安定法で定められた許可基準を委託者と受託者がそれぞれ満たす必要があります。許可基準の詳細な要件については後ほど解説するので、引き続きご覧ください。
採用代行(RPO)に業務を委託する際に違法となるリスクとは?
先述した通り、委託募集に当たる採用代行を利用する場合は、委託者と受託者の両方がしかるべき相手から許可を得る必要があります。裏を返せば、両者が許可を取った上での利用であれば、採用代行に何ら違法性はないのです。
ここでは、この点に関わる採用代行と法律の関係性をさらに深掘りしていきます。
基準を満たしていれば違法ではない
繰り返しになりますが、委託者と受託者が職業安定法で定められた基準を満たして許可を取得すれば、採用代行による人材の採用は合法となります。この点には、以下に記した職業安定法第36条1項と同法第60条、そして同法施行規則第37条1項3号が関係しています。
(委託募集)
第三十六条 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(引用:e-gov法令検索『職業安定法』)
(権限の委任)
第六十条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、職業安定主管局長又は都道府県労働局長に委任することができる。
(引用:e-gov法令検索『職業安定法』)
(法第六十条に関する事項)
第三十七条 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
三 法第三十二条の九第二項(法第三十三条第四項及び法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
(引用:e-gov法令検索『職業安定法施行規則』)
では、具体的にどのような対応を取れば、厚生労働大臣または都道府県労働局長から許可を得られるのでしょうか?
この点は、厚生労働省から提示されている「委託募集の許可基準」に詳細な記載があります。委託募集を行うためには、同資料内で定められた「労働関係法に違反していないこと」や「適切な労働条件を設定していること」などの基準を満たさなくてはなりません。
こうした許可基準が設けられている背景には、「労働者の権利や安全を保護する」という目的があります。労働者が不利な条件で雇用されてしまうことがないように、委託募集が可能な企業の適格性を法律により規定する必要があるのです。
(参照:厚生労働省『募集・求人業務取扱要領 Ⅲ 委託募集 』)
違法の可能性があるケース
許可を得ずに委託募集に当たる採用代行を行った場合は、当然違法となります。
ここで注意したい点が、受託者、つまり採用代行業者側が許可を得ていない可能性もある、という部分です。この場合、たとえ利用者側が許可を得ていたとしても、違法行為になってしまう恐れがあるのです。
予期せぬトラブルに巻き込まれることを防ぐためにも、採用代行を利用する際は委託先が適切な許可を得ているかどうかを必ず確認しましょう。
採用代行(RPO)を利用する際は必ず許可が必要?
実は、採用代行の全てが委託募集に該当するわけではありません。採用代行を利用する際の条件次第では、委託者に関しては許可を取らなくても良い場合があります。
ここでは、その委託募集に該当しないケースと該当するケースの違いを解説します。
委託側の許可が不要のケース
委託する業務の範囲や人材を募集する際の経路によっては、採用代行が委託募集として見なされず、委託者側で許可を取る必要がなくなります。
例えば、転職希望者の募集や選考は自社で行い、採用試験問題の作成や実施といった業務だけを外部に委託する場合は、委託募集にはなりません。つまり、職業安定法の「募集」に当たる行為を第三者に委託しないのであれば、委託募集としては見なされないのです。
委託募集にならない業務としては、上記のほかにも以下が挙げられます。
委託募集に該当しない業務
- 採用要件やKPIの設定
- 求人広告の作成
- スカウトメールの送信
採用代行を利用する際は、まず業者に任せたい業務を整理した上で、それが委託募集に当たるかどうかを確認しましょう。
委託側の許可が必要なケース
反対に、職業安定法の「募集」に当たる行為を外部に委託する場合は、委託募集となり許可を取る必要が生じます。その際は、先述した委託募集の許可基準を委託者と受託者が満たさなくてはならないわけですが、実はそれぞれの基準には違いが存在します。
委託募集での許可基準の違い
- 委託側の基準
- 受託側の基準
- 募集期間や報酬の認可基準
委託側の基準
採用代行の委託者は、以下の基準を満たすことが要求されます。
委託側の基準
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 事業主の要件 | 職業安定法および労働関係法令に重大な違反がないこと |
| 募集に係る労働条件 |
・労働条件が適切で、法令に違反するものではないこと ・同地域・同業種の賃金水準と比べて著しく低い金額ではないこと ・業務内容や労働条件が明示されていること ・適用事業所が社会・労働保険に加入していること |
| 報酬 | 厚生労働大臣の認可を受けた報酬以外の財物を与えるものではないこと |
いずれの内容も、健全な企業経営を行っていれば問題なくクリアできるものとなっています。そのため、利用の際に改めて何か対策を講じる必要はないでしょう。
(参照:厚生労働省『募集・求人業務取扱要領 Ⅲ 委託募集』)
受託側の基準
対して、受託者に定められた基準は以下の通りです。
受託側の基準
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 事業主の要件 | 職業安定法および労働関係法令に重大な違反がないこと |
| 業務に必要な判断能力 | 精神の機能の障害により労働者の募集を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと |
| 採用代行に必要な知識 | 労働関係法令や募集内容、職種に関して十分な知識を持っていること |
関連法に違反していないという基本的な事項に加えて、採用代行を行う上で必要な判断能力や知識を持っているかどうかが問われます。
(参照:厚生労働省『募集・求人業務取扱要領 Ⅲ 委託募集』)
募集期間や報酬の認可基準
委託者・受託者のそれぞれに対する基準のほかに、募集期間や報酬について定めた認可基準も存在します。
募集期間や報酬の認可基準
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 募集期間 | 募集を行おうとする期間が1年を超えないこと |
| 報酬 |
支払われた資金額の100分の50を超えないこと ※委託募集に要する経費が特に高額となる特段の事情がある場合を除く |
委託者の基準と同様に、健全な企業経営ができていれば容易に満たせる条件となっています。
しかし、採用代行を利用するに当たって重要な基準となることに変わりはありません。これらの基準を参考に、信頼できる採用代行業者を選ぶことが大切です。
(参照:厚生労働省『募集・求人業務取扱要領 Ⅲ 委託募集』)

委託募集の許可を申請する方法と手順
採用代行を利用するために許可を申請する際は、以下の手順に従って手続きを進めましょう。
委託募集の許可を申請する方法と手順
- 1.委託募集の申請に必要な書類を用意する
- 2.提出先が厚生労働大臣か労働局長かを確認する
- 3.書類の提出期限を確認し提出する
- 4.審査結果を待つ
各ステップの詳細を順に解説します。
STEP①委託募集の申請に必要な書類を用意する
まずは、申請に必要な「委託募集許可等申請書(様式第3号)」を準備しましょう。厚生労働省が配布を行っており、インターネットから簡単に入手可能です。
また、本書類の提出時には、その内容を証明するための帳簿なども提出を求められる場合があるため、併せて準備しておくことをお勧めします。
(参照:厚生労働省『委託募集許可等申請書 委託募集届出書』
STEP②提出先が厚生労働大臣か労働局長かを確認する
用意した書類の提出先は、採用代行で募集する人材の人数に応じて変わります。以下の条件いずれかに該当する場合は、厚生労働大臣へ書類を提出しましょう。
書類を厚生労働大臣に提出する場合の条件、自県外募集で次のいずれかに該当するもの
- 1つの都道府県から30人以上募集する
- 募集人数が100人以上になる
上記のいずれにも該当しない場合は、都道府県労働局長へ提出することとなります。
STEP③書類の提出期限を確認し提出する
書類の準備が完了したら、後は提出するだけですが、この際、提出先の違いによって提出期限も変わる点に注意が必要です。厚生労働大臣に提出する場合は募集開始月の21日前まで、都道府県労働局長の場合は14日前までとなります。
STEP④審査結果を待つ
書類の提出後は、許可基準の内容に基づいた審査が行われます。この審査結果が「許可」あるいは「条件付き許可」の場合は、採用代行を利用しても問題ないと認められたことになります。
なお、委託者側の一連の申請作業は、受託者に代行を依頼しても問題ありません。申請作業にあまり時間を割きたくない、あるいはノウハウがないためプロに任せたいなどの事情があるなら、委託先に相談することをお勧めします。
採用代行(RPO)を利用する際に違法リスクを回避するための注意点
採用代行の利用時には、以下の点に注意して違法行為のリスクを回避することが非常に大切です。
採用代行(RPO)を利用する際の注意点
- 信頼できる業者を選定する
- 法律の専門家を活用する
- 社員教育を行う
法律にのっとった形で採用代行を利用することが、企業としての責任ある行いだといえます。
信頼できる業者を選定する
自社が委託募集の許可を得ていたとしても、委託先の業者に問題があって、知らずのうちに違法行為に携わってしまうことがあるかもしれません。そのため、委託先を選定する際は必ず以下の内容をリサーチして、信頼性の有無を確認しましょう。
業者選定の際に確認したいポイント
- 職業紹介事業許可があるか
- 自社の業種に関する知見や専門性があるか
- 採用代行の十分な実績があるか
- 口コミや評判に問題がないか
- こちらの要望に合わせた柔軟な対応が期待できるか
この中でも優先的に確認したい点が、職業紹介事業許可の有無です。
採用代行などの職業紹介行為を行うためには、厚生労働省から上記の許可を得なくてはなりません。この許可を得ていない業者はそもそも採用代行業者として不適格であるので、候補から外す必要があります。

法律の専門家を活用する
「法律に違反するリスクを自社だけで回避できるだろうか…」と不安な場合は、顧問弁護士や社会保険労務士の手を借りることもお勧めします。
顧問弁護士には、採用代行利用時の契約書の確認や、万が一法的トラブルに発展してしまった場合の対応などを依頼できます。労働基準法に基づいた労働条件の設定や、応募があった転職希望者の個人情報の管理など、労務に関する部分は社会保険労務士に任せましょう。
上記以外にも、労働局が設置している相談窓口や、自社の属する業界団体のガイドラインなども積極的に活用したいところです。
社員教育を行う
採用業務に関わる社員に、法律や採用についての適切な教育を実施することも重要です。特に、職業安定法と労働基準法、個人情報保護法の3つは採用代行にも関係するため、条文の内容や業務上の注意点などを研修で優先的にレクチャーすることをお勧めします。
上記に加えて、「法令を順守する」というコンプライアンス意識を社内全体で醸成することも、欠かせない対応といえます。法律に精通していたとしても、それを守るという意識が欠けていては元も子もありません。
違法行為を行った際に会社が被る損害、そして社会的な問題の大きさなどを繰り返し周知して、コンプライアンス意識を育んでいくことが大切です。より確実に違法行為や不正を防止するために、内部監査を実施して法令順守状況を定期的にチェックしてもよいでしょう。
採用代行業者に依頼する際のポイント
最後に、採用代行で業務を依頼する際に意識したいポイントを解説します。以下の2点を意識すれば、より効率良く採用活動を進められるでしょう。
採用代行業者に依頼する際のポイント
- 委託する業務を明確にする
- 採用課題や要件などの情報を共有する
委託する業務を明確にする
委託する採用業務の範囲を明確にし、自社と採用代行業者の役割分担をはっきりと分けることは、採用活動の効率化を図る上で必要不可欠です。
採用業務と一口にいってもその種類はさまざまであり、企業によっては人事・採用担当者も全貌を把握できていないケースが少なくありません。そのため、業者へ委託する前に、まずは自社内で採用業務の棚卸しを行いましょう。
その上で、自社でカバーする領域と委託する領域を分ければ、作業の重複や抜け漏れを発生させることなく採用活動を進められます。
採用課題や要件などの情報を共有する
自社が抱えている採用課題や求める人材像などの情報は、採用代行業者へ積極的に共有しましょう。採用代行業者が自社の現状を正確に把握すれば、アプローチの精度が向上し、自社にマッチした人材を採用できる可能性が高まります。
また、こうした情報共有をスムーズに行うためには、お互いがコミュニケーションを取りやすい環境をつくることも欠かせません。そのためには、コミュニケーションに用いるツールの種類や、情報共有を行うベストなタイミングなどについて、事前に擦り合わせを済ませておきたいところです。
一方的に採用業務を任せるのではなく、業者と共に協力し合える体制を構築することが、採用活動の成功につながります。
適切な手順を踏みしかるべき相手から許可を得ているなら、採用代行に違法性はない
今回は、採用代行が違法になるケースとならないケースの違いを解説しました。
採用代行は、適切な手順を踏み許可を得ているのであれば合法ですが、委託先の法令順守状況によっては、知らずのうちに違法行為になってしまうことがあるかもしれません。そのような事態を避けるためにも、採用代行業者を選ぶ際は許可の有無や実績などを入念に確認しましょう。
採用代行以外にもさまざまな採用手法を検討したいのであれば、ぜひ「doda」にお問い合わせください。「doda人材紹介」や「doda求人情報」、「doda ダイレクト」などの多種多様なサービスの中から、貴社の状況に最適なものをピックアップしてご提案いたします。
(監修協力/弁護士法人ブライト 弁護士 和氣良浩 )
採用コスト削減につながった
doda導入・採用成功事例
おすすめ記事
採用代行は違法?許可の申請手順や法令順守しながら活用するポイントページです。【中途採用をお考えの法人様へ】dodaサービスのご案内 - 採用成功への扉を開く、総合採用支援サービス