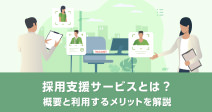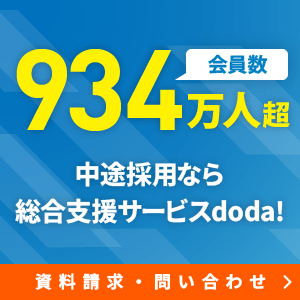2025.11.27
中途採用のキホン
採用活動の成功には、明確に定めた採用要件が必須です。しかし、採用要件の詳細を把握できていない、また既存の要件がうまく活用できていないケースは少なくありません。
特に、初めて採用に取り組む企業や、新たに人事・採用担当者を起用した場合に起こり得ます。
本記事では採用要件の概要を、手順や注意点とともにご紹介します。最適な採用要件で選考の精度を高め、自社が求める人材を確実に採用するための参考にしてください。

採用要件(人材要件)とは?
採用要件(人材要件)とは、採用活動を通して自社が希望する人材像の基準を、明確に定めたものを指します。要件を満たした人材は採用へ、満たしていない人材は不採用といったように採否の基準となるため、細かい言語化が必要です。
設定する要件としては、転職希望者の人柄や経歴、スキル、所有している資格をはじめ、はたらく上での価値観などが挙げられます。
採用要件を適切に定めていない場合、早期離職につながったり、パフォーマンスを最大に発揮できなかったりと、双方にとって悪い結果を招きかねません。
採用要件と採用ペルソナの違い
採用要件と似た言葉に、「採用ペルソナ」があります。採用ペルソナは、自社として採用したい人材の具体的な人材像です。採用要件が大まかな人材像を指しているのに対して、採用ペルソナは1人の架空の人材像を示している点が大きな違いです。
採用ペルソナでは、定めた採用要件を基に採用したい人材の年齢や性別、ライフスタイルなどのパーソナリティとなる部分をより明確に決めていきます。つまり採用ペルソナを決めるための諸条件が、採用要件ということです。
採用ペルソナは、人材要件を言語化するためのプロセスとなるため、具体的な内容を落とし込むことが大切です。ペルソナを明確に固めておけば、採用要件の粒度も細かくなり、人事・採用担当者間で連携が取りやすくなります。
採用要件を定義する目的
採用要件を明確に定めることには、以下に挙げる4つの目的があります。
採用要件を定義する目的
- 求める人材像を明確化するため
- 採用ミスマッチを防止するため
- 選考基準を統一するため
- 採用手法や選考方法を定めるため
求める人材像を明確化するため
採用要件を作成すると、自社が求めている人材像が明確になり、「どの層にアプローチすると良いか」「どのようにアプローチするのが良いか」などを検討しやすくなります。
求める人材像が明確になると、転職希望者に期待するはたらきや任せたい業務内容、そして必要な能力や経験といった部分も明らかにできます。詳細に示された人材像に基づく選考で、入社後に活躍する人材の採用につながる可能性を高められるでしょう。
関連記事:採用手法一覧 中途採用に役立つ採用手法の種類や比較などを総まとめ
採用ミスマッチを防止するため
採用要件の具体的な設定をすることで、採用活動の質が高くなり採用後のミスマッチの防止につながります。これは、人事・採用担当者間で採用指針を共有することで、採用活動全体の認識のずれが生じづらくなるためです。
採用要件があいまいだと、採用活動を通して担当者ごとに異なる基準が生まれ、自社が求める人材を採用できません。あるいは、企業文化や価値観の相違から入社後のギャップにつながり、早期離職へと発展する恐れもあるでしょう。
適切に定めた基準に沿って選考を進めるためにも、採用要件の定義が必要なのです。
選考基準を統一するため
採用要件の設定は、公平かつ客観的な評価に基づいた選考基準の統一にもつながります。どれほど経験を積んだ面接官でも、評価の際には主観を含んでしまうものです。しかし、主観や感覚だけに頼ってしまうと、条件に合わない人材を採用してしまったり、反対に希望に合う人材を採用できなかったりする可能性があります。
面接官の主観によって、合否が分かれる選考は公正とはいえません。
その点、採用要件を定義していれば人材を見極める基準が明確であるため、人事・採用担当者に左右されない採用活動につながるでしょう。
関連記事:採用基準とは? 決め方、見直す項目やポイントと注意点を解説
採用手法や選考方法を定めるため
採用要件を定義すると、選考で見極める必要のある項目が明確になるため、適切な採用手法・選考方法を見いだせます。
売り手市場によって転職希望者側も選ぶ立場となる近年では、企業側には採用手法や選考方法にも工夫を凝らすことが求められます。従来まで主流だった求人広告だけでは応募数を担保できない可能性があるため、ダイレクト・ソーシングやリファラル採用など、あらゆる採用手法を模索することが重要です。
また、選考方法も面接だけでなく、採用要件に合致する人材を採用するための手段を取り入れましょう。例えば、言語力や論理的思考力といった基礎学力を優先的に求めるのであれば、SPIの実施が有効です。
採用要件のつくり方
採用要件を定める場合、主に2つの方法があります。
以下でそれぞれの特徴をご紹介するので、違いを押さえた上で自社に合う方法を選びましょう。
採用要件のつくり方
- 組織や事業の目標から逆算して作成する方法【演繹的アプローチ】
- 自社の活躍している人材から作成する方法【帰納的アプローチ】
組織や事業の目標から逆算して作成する方法【演繹的アプローチ】
演繹(えんえき)的アプローチは、採用要件を定義する上で一般的に紹介される方法です。自社が目指す将来像から求める要件を検討するため、企業の組織づくりに直結する方法といえます。
具体的な手順を以下で確認しましょう。
演繹的アプローチの手順
- STEP1.企業方針・事業計画を確認する
- STEP2.募集職種の業務内容を洗い出す
- STEP3.現場へのヒアリングで必要要件を整理
- STEP4.要件をMUST・WANTに分類し優先度を設定する
- STEP5.採用ペルソナを設定して人材像を固める
STEP1.企業方針・事業計画を確認する
まずは、自社の方針や事業計画を確認した上で、採用要件の方向性を明確にします。
企業理念やビジョンは中長期的に設定するものですが、経営状況や社会情勢によって変わる可能性があります。これらを決定している経営陣にヒアリングして最新のものを確認しましょう。
STEP2.募集職種の業務内容を洗い出す
企業方針や事業計画を基に人材像が固まれば、職種の業務内容や必要なスキル・経験などを洗い出します。これにより、募集職種の業務内容や求めるスキルに適性のある人材を採用できるチャンスを広げます。
特に、募集職種の担当者とは別の担当者が採用活動にあたる場合は、この段階でできる限り具体的に洗い出しましょう。この工程があいまいになると、要望に添わない採用につながる恐れがあります。
STEP3.現場へのヒアリングで必要要件を整理
続いて、新たに人材を募集する部署にヒアリングして、人材に求める要件を整理していきます。
採用要件は人事・採用担当者のみで定めるものではありません。人材が配属されることとなる現場の意見も取り入れなければ、雰囲気になじむ人材の採用につながらないためです。
入社後の定着を目指すためにも、現場として、どのような価値観や性格特性、考え方などを有している人材を求めているのかを明確にしましょう。
STEP4.要件をMUST・WANTに分類し優先度を設定する
人材に求める要件が整理できたら、それらに優先順位をつけます。
洗い出した要件すべてを持ち合わせた人材を採用できると理想ですが、現実的には難しいでしょう。そうしたときに、どの要件を満たしていれば採用ラインなのか、要件ごとに優先順位を設ける必要があるのです。
優先順位を設定する場合は、「MUST:必ず満たすべき要件」あるいは「WANT:満たしていれば加点する要件」の2つに大別して分類することが効率的です。中でもMUSTは、満たしていなければ不採用とする基準となるため、人材を見極めることもスムーズになります。
STEP5.採用ペルソナを設定して人材像を固める
ここまでの流れを踏まえて出た要件とは別に、数字で表しにくい定量的な要件も挙げて採用ペルソナを設定しましょう。客観的に判断できるスキルや経験、所有資格のみで人材を採用すると、採用後のミスマッチにつながるリスクがあります。
採用ペルソナに基づいて人材像を設定したら、採用要件の策定は完了です。
完成した採用要件は、重要性を理解してもらえるように人事・採用担当者など関係各所に周知します。
自社の活躍している人材から作成する方法【帰納的アプローチ】
帰納的アプローチは、すでに社内で活躍している人材を分析し、その要因を基に要件を定義する方法です。その人材の能力や行動特性などを把握し、どのような条件であれば自社に合うのかを洗い出します。
帰納的アプローチの手順
- STEP1.活躍している社員の特定・リストアップ
- STEP2.活躍している社員のキャリアの洗い出し
- STEP3.スキルや能力の共通点を明確にする
- STEP4.採用ペルソナを設定して人材像を固める
STEP1.活躍している社員の特定・リストアップ
帰納的アプローチを取り入れる場合、最初に行うことはモデルとなる活躍社員の選抜です。この段階で1人に絞る必要はないので、配属を予定している部署の中で明確に活躍している社員を複数名リストアップしましょう。複数名のほうが、共通する要件を洗い出しやすいのでお勧めです。
なお、新卒採用のように、採用後に配属する部署が定まっていない場合は、部署を問わずに各部署内で高い評価を得ている社員を選抜します。
STEP2.活躍している社員のキャリアの洗い出し
次に活躍している社員全員にヒアリングを行い、これまでのキャリアを確認します。
中途社員であればスキルや経験、保有資格などで、新卒社員の場合は学歴や学生時代の活動などです。
STEP3.スキルや能力の共通点を明確にする
ヒアリングした内容を踏まえて、活躍社員に共通する要件を特定しましょう。
「なぜ活躍できているのか」「どのように成果を出しているのか」といった観点から、スキルや能力といった共通点を見出します。
STEP1の段階で活躍社員を複数名ピックアップしている場合は、この共通点が採用要件となるケースがほとんどです。
STEP4.採用ペルソナを設定して人材像を固める
洗い出した共通点に優先順位を設けたら、演繹的アプローチと同じように採用ペルソナを設定して、採用要件を固めます。
帰納的アプローチは実在する人物を基準とするため、演繹的アプローチと比較して採用要件の定義が容易といえます。
採用要件をつくる際に役立つフレームワーク
採用要件を初めて作成する場合や、従来の採用要件ではうまく成果につながっていない場合には、フレームワークを活用することも手です。
採用要件づくりに役立つフレームワーク
- MUST・WANT・BETTER・NEGATIVE
- コンピテンシーモデル
- STP
MUST・WANT・BETTER・NEGATIVE
人材要件のフレームワークとして、上述した「MUST」「WANT」に「BETTER」「NEGATIVE」を加えた4要素を活用してみましょう。これらは人材要件を定めるにあたり、洗い出した人材に求める条件に優先順位を設定する際に有効です。
それぞれの優先度分けは以下に挙げた通りです。
優先度分けの4要素
- MUST:必要要件
- WANT:十分要件
- BETTER:歓迎要件
- NEGATIVE:不要要件
このフレームワークを活用する際は、まずMUSTとNEGATIVEの2項目に大きく条件を分けます。MUSTに分類した中で必須条件ではないと判断した条件を、優先度順にWANT、そしてBETTERへと振り分けるイメージです。
人材に求めない不要条件も決めておくことで、選考をよりスムーズに進められるはずです。
コンピテンシーモデル
採用要件のフレームワークとしては、コンピテンシーモデルも挙げられます。
コンピテンシーモデルとは、社内で活躍している社員の行動・性格特性を分析して、理想の人材像を定義することです。
コンピテンシーモデルの設計手順
- 1.アンケートや適性検査の実施などで活躍している社員の行動・性格特性を調査する
- 2.活躍社員の共通点を洗い出す
- 3.共通点を求める人材像に落とし込む
採用要件を新たに設定する際には、自社のコンピテンシーモデルを明らかにしておくことで、すでに活躍している社員により近い人材の採用が期待できます。
STP
特に新卒採用向けのフレームワークとしては、STP法が挙げられます。STP法は「Segmentation:市場の細分化」「Targeting:ターゲット分析」「Positioning:自社の立ち位置分析」という流れを用いるマーケティング手法です。
STP法では、まず新卒採用市場を学科や学部、所属ゼミ・サークルといった基準で細分化して、自社が求めるグループを定めます。アプローチするグループが決まれば、他社と差別化できる採用戦略を構築し、適切に採用活動を行います。

採用要件のフォーマット
続いて、採用要件を設定する際に有用なフォーマットと、その記入例をご紹介します。
採用要件のフォーマット
| 優先度 | 採用要件 | 要件の種類(1つのみ〇) | 判定方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MUST(必要要件) | 経験・スキル/能力/価値観 | |||
| 経験・スキル/能力/価値観 | ||||
| 経験・スキル/能力/価値観 | ||||
| WANT(十分要件) | 経験・スキル/能力/価値観 | |||
| 経験・スキル/能力/価値観 | ||||
| 経験・スキル/能力/価値観 | ||||
| BETTER(歓迎要件) | 経験・スキル/能力/価値観 | |||
| 経験・スキル/能力/価値観 | ||||
| 経験・スキル/能力/価値観 | ||||
| NEGATIVE(不要要件) | 経験・スキル/能力/価値観 | |||
| 経験・スキル/能力/価値観 | ||||
| 経験・スキル/能力/価値観 |
採用要件のフォーマット記入例
| 優先度 | 採用要件 | 要件の種類(1つのみ〇) | 判定方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MUST(必要要件) | コミュニケーション能力 | 経験・スキル/(能力)/価値観 |
・面接 ・記述試験 |
|
| WANT(十分要件) | 3年以上の営業経験 | 経験・(スキル)/能力/価値観 | ・書類選考 | |
| BETTER(歓迎要件) | 経営者・大企業への営業経験 | (経験)・スキル/能力/価値観 | ・面接 | |
| NEGATIVE(不要要件) | コンプライアンス意識の低さ | 経験・スキル/能力/価値観 | ・面接 | 当てはまる場合は不採用 |
上記は一例のため、各項目の種類が1つしかありませんが、候補に挙がった採用要件はすべて記入し、関係者間での意見交換で取捨選択すると精度を高められます。
採用要件の具体例・項目例
採用要件の作成について流れは押さえたものの、具体的にはどのように決めていくと良いのでしょうか。
以下で、中途採用と職種別に分けて、採用要件の具体例をご紹介します。
中途採用の例
中途採用では、一般的にこれまでの経験・スキルや社歴などが重視されます。
しかし、経験やスキルは自社にマッチしているにもかかわらず、採用後に早期離職につながるケースは少なくありません。
これは、企業側の社風やビジョンと、転職希望者の価値観や考え方などがマッチしていないために起こります。
こうしたミスマッチを防ぐには、経験やスキルだけでなく、転職希望者が持つ特徴が自社にマッチしているかどうかという観点で要件を作成しましょう。具体的には、「コミュニケーション能力」「ビジネスマナー」「ストレス耐性」などが挙げられます。
職種別の採用要件の例
ここからは、中途採用の中でもさらに職種を絞って、営業職とエンジニアで設定される採用要件の例をご紹介します。
営業職の例
営業職の場合、対人スキルが求められるため、そうした経験やスキルを重視する傾向にあります。しかし、ひと口にコミュニケーション能力といっても、その基準は人それぞれでしょう。あいまいな採用要件にならないよう、活躍している営業社員をピックアップした上で、人柄や能力、業務内容、属性などを細かく分析して「自社にマッチした営業社員」を定義することが大切です。
そうして定めた人材像から、採用要件を抜き出します。論理的思考能力や課題解決能力といったスキルから、「3年以上の営業経験」「相手の課題に対して提案、解決した経験」などの具体的な経験が挙げられます。
エンジニアの例
エンジニアを中途で採用する場合は、即戦力として活躍できる採用要件の作成が必要です。
必要要件としては「JavaScriptの実務経験3年以上」「スマートフォン向けのアプリケーション開発の実務経験3年以上」といった、経験やスキルを明確に設定します。対応可能言語や、自社・受託開発のいずれに携わったのかなどを要件として設けることもお勧めです。
また、上記以外に「コツコツ学習を続けられる」「チーム単位で開発することを好む」などの要素を含めると、価値観の相違による早期離職も防げるでしょう。
なお、未経験のエンジニアを採用したい場合は、スクールの有無やIT・技術への関心などを測れる要件を加え、エンジニアとしての適性や意欲などを重視することが重要です。
採用要件をつくる際に重要なポイント
採用要件を作成する際には、以下に挙げる4つのポイントを意識しましょう。
採用要件をつくる際のポイント
- 企業理念・価値観との一貫性を持たせる
- 転職希望者・競合、自社(3C)の視点を考慮する
- 完成した要件を採用チームで共有・周知する
- 定期的に見直し・改善する
企業理念・価値観との一貫性を持たせる
まず挙げられるポイントが、理念や価値観など、企業の方向性との一貫性を持った採用要件をつくることです。これに一貫性がないと、入社後のギャップが大きくなり早期離職につながる恐れがあります。
ほかにも、同じ価値観に向けた基盤づくりは組織全体に良い影響を与えます。共通の価値観に沿った基盤づくりが構築されると、新たに入社した社員が組織文化に適応しやすくなり、組織一丸となって同じ目標に向けた協力体制を築けるはずです。
転職希望者・競合、自社(3C)の視点を考慮する
採用活動では、「転職希望者:Customer」「他社:Competitor」「自社:Company」の3Cの視点から要件を考えましょう。自社のみにフォーカスがあたった採用要件には要注意です。
例えば、自社として必要とする採用要件を設定したものの、「ハードルが高過ぎて、市場に合致する人材がほとんどいない」「他社とほとんど同じ要件で、なかなか採用に至らない」という結果を招くケースがあります。
この場合、転職希望者や採用市場にも目を向けて、一定の応募数が担保できるレベルにまで調整したり、競合他社の採用要件を確認して差別化を図ったりすることが有効です。
完成した要件を採用チームで共有・周知する
さまざまな工夫を凝らして完成した採用要件は、採用活動に関係する担当者全員に確実に共有・周知しましょう。人事・採用担当者をはじめ、面接官を依頼する社員、説明会やインターンシップに協力してくれる社員など、漏れなく共有してください。
関係者と要件を共有することで、転職希望者を見極める際の視点が統一され、面接での質問や言い回しの精度の向上が期待できます。
定期的に見直し・改善する
採用要件は一度作成したらそれで終わりではありません。
社会の風潮や技術革新などにより、採用市場は日々変化し続けています。そのため、市場の変化や競合他社の動向を常に注視して、人材に求める要件をブラッシュアップしていく必要があるのです。
採用要件を見直す場合は、既存の要件を参考にした上で、現状に必要な人材に求める要件がそろっているかどうかを確認しましょう。自社が希望する人材を採用できるよう、要件の過不足を適宜見直すことが大切です。

採用要件をつくる際の注意点
最後に、採用要件を新たに作成する際の注意点を3つご紹介します。
採用要件をつくる際の注意点
- 要件を増やし過ぎない
- 客観的に判断できる基準にする
- 人材の多様性を損なわないようにする
要件を増やし過ぎない
採用要件を検討する際は、増やし過ぎに注意してください。
新たに人材を採用するにあたっては、転職希望者に求める条件がつい多くなりがちです。しかし、採用要件の数が多過ぎると、現実的でない人材像ができあがり、成果につながる可能性が低くなってしまいます。
経験やスキル、能力などで要件の候補を上げる際は、ある程度項目を絞り、応募が集まるよう、適切な数にまとめましょう。
客観的に判断できる基準にする
採用要件には主観的ではなく、客観的に判断できる基準を設けることも大切です。採用要件に主観的な要素が含まれていると、公正な評価が難しくなるため、自社が求める人材の採用につながらない可能性があります。
例えば、業務に必要な資格や過去の経験年数などは、誰でも評価できる基準です。一方、積極性や自主性などは企業にとって求めたい要素ですが、客観的な判断が難しい要素ともいえます。
主観的な要素をできる限り含めないためにも、作成時には分析ツールを取り入れる、また定量的なデータを活用するといった工夫が有効です。
人材の多様性を損なわないようにする
採用要件は基準を満たした転職希望者を見極める際に役立つものですが、人材の多様性を損なうような偏った項目にならないように注意しなければなりません。
例えば一度に多くの人材を採用したい場合に、偏った採用要件に基づいて評価すると、採用に至った転職希望者が、同じような人材で固定されてしまう可能性があります。
採用の目的に合わせて使い分けられるよう、上述の注意点を抑えた上であらゆるケースに適応できる採用要件を作成することをお勧めします。
採用要件は、採用活動で自社が人材に求める基準を明確に定義したもの
採用要件を定義することは自社が求める人材像を明確にできるため、転職希望者を客観的に評価しやすく、採用後のミスマッチを防げるといった利点があります。
新たな要件は、自社の将来像から逆算する方法か、自社内で活躍している人材の共通点から洗い出す方法のいずれかから作成します。なお、作成時は客観的に評価できる要件を盛り込み、また、要件の数は増やしすぎないように注意してください。
「採用要件を設定したが、採用活動がうまく進まない」「今の採用要件が適しているのかわからない」このようなお悩みを抱えている際には、「doda」にご相談ください。
豊富なサービスラインアップの中から、専任の担当者が貴社の採用課題を解決に導ける方法をご提案いたします。
中途採用なら総合支援サービスdoda
doda採用支援サービス一覧

採用コスト削減につながった
doda導入・採用成功事例
おすすめ記事
採用要件(人材要件)とは?つくり方の手順や注意点、具体例まで解説ページです。【中途採用をお考えの法人様へ】dodaサービスのご案内 - 採用成功への扉を開く、総合採用支援サービス