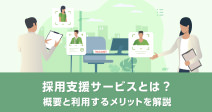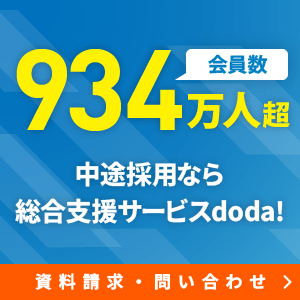2025.09.24
中途採用のキホン
社内で欠員が出た場合は、代わりとなる人材を採用する必要があります。その際に適切な対応を行わなければ、業務に支障をきたし、大きな損失を被ってしまうかもしれません。
本記事の内容をよく確認して、このような事態を未然に防ぎましょう。

欠員補充とは
欠員補充とは、異動や退職、長期休暇などによって社内のポジションが空いた場合に、その補填として新たな人材を採用することです。ポジションが空いたままでは、業務が回らなくなってしまう可能性もあるため、欠員補充の際には迅速な対応が求められます。
なお、人材を管理する上で最も大切なポイントは、「急な退職による欠員をできる限り出さないこと」です。詳しくは後述しますが、離職抑止の取り組みを日頃から実施できると理想です。
効果的な欠員補充の対応手順
欠員補充は、以下の手順で進めていくことが一般的です。
欠員補充の対応手順
- 手順1.欠員が発生している業務内容を把握し、人材要件を定義する
- 手順2.社内の人員の再配置を行う
- 手順3.入念に準備してから採用活動を行う
- 手順4.社員のフォローを行う
- 手順5.欠員対策を検討する
手順1.欠員が発生している業務内容を把握し、人材要件を定義する
まずは欠員が出ているポジションの業務内容を把握し、「欠員を埋めるにはどのような人材が必要なのか」を明確にします。
このときに意識したい点は、経験やスキルだけでなく、企業文化との適合性も考慮して人材要件を定めることです。企業になじめずに早期離職されてしまうリスクを減らせるため、長期的な活躍が期待できるでしょう。
手順2.社内の人員の再配置を行う
人材要件を明確にした後は、代わりの人材を採用するまでの間、業務を滞りなく進めるために人員を再配置します。その際には、特定の人材に負担が偏らないよう、空いたポジションの役割を適切に割り振ることが重要です。負担が一部の人材に集中すると、業務の質やモチベーションの低下を招いてしまうかもしれません。
なお、「社内のリソースだけでは欠員を補えない…」という場合は、社外の人材の力を一時的に借りることも一つの手です。
手順3.入念に準備してから採用活動を行う
次に、採用活動を行うための準備を始めます。事前に定めた人材要件を基に、「いつまでに何人採用するのか」「どのような手法で採用活動を進めるのか」などを社内でよく検討しましょう。こうした準備を入念に行っておくことで、その後の取り組みを円滑に進められるようになります。
準備が整い次第、採用活動に移ります。その際は、初期費用を抑えたい場合は成果報酬型のサービス、工数を削減したい場合は人材紹介サービスといった具合に、適切な手法で人材を集めることがポイントです。
関連記事:採用活動とは?企業側における成功ポイントや採用トレンドをご紹介
手順4.社員のフォローを行う
社内で欠員が発生すると、既存社員は「この先、業務を回していけるのだろうか…」と不安になります。そのままでは業務に支障を来す恐れもあるため、既存社員に欠員の状況や今後の採用計画などを包み隠さずに共有し、不安を解消することが大切です。
また同時に、イレギュラーな状況に対応してくれていることへの感謝を伝えれば、社員の業務に対するモチベーションを高く保てるはずです。
手順5.欠員対策を検討する
欠員補充に成功したら、人材を長期的に定着させるために、欠員を防ぐ取り組みを検討します。これまでに発生した欠員の理由をリストアップし、社内制度や企業文化を見直すと良いでしょう。
具体的な対策は、本記事の後半でご紹介します。
欠員補充で意識したいポイント
ここでは、欠員補充を実施する際に押さえておきたい3つのポイントを解説します。自社で行うときのイメージをつかむために役立ててください。
欠員補充の際に押さえておきたいポイント
- ポイント1.魅力的な求人票を作成する
- ポイント2.目的に応じた採用手法を選定する
- ポイント3.採用プロセスを最適化しスピーディーに対応する
ポイント1.魅力的な求人票を作成する
欠員補充を目的とした採用活動では、読み手が「応募したい!」と感じるような求人票を作成する必要があります。
求人票は、人材が自社を認知するきっかけとなります。記載内容が魅力的でなければ、応募がなかなか集まらず、欠員補充が難航するかもしれません。ポジションに長い期間空きがあると、業務が滞って大きな損失を招くことも考えられます。
こうした事態を避けるためにも、求人票の作成時には次の2点を意識したいところです。
求人票を魅力的に見せるためのコツ
- 募集背景の書き方を工夫する
- 人材が知りたい内容を意識して記載する
募集背景の書き方を工夫する
募集背景は、ポジティブな要素を加えて記載しましょう。
例えば人材の異動を理由に欠員補充を行うのであれば、募集背景に「体制の見直しのため」と記載することで、ポジティブな印象を与えられます。そのほか退職を理由とする場合には、「組織強化のため」という表現もできます。
また募集背景では、単に欠員補充の目的のみを記載するのではなく、応募の動機付けとなる文言を盛り込むことも大切です。「組織の形成に関わることができる」「特定のスキルを活かせる」などと記載し、人材の興味を引けると望ましいです。
関連記事:求人票の書き方を解説。記載してはいけないNG項目から応募につながるコツまでを紹介
人材が知りたい内容を意識して記載する
人材が知りたい情報を取り入れることで、求人票を魅力的に感じてもらえる可能性が高まります。具体的には、次の情報を記載することが一般的です。
求人票に記載する情報の例
- 業務内容
- 企業文化
- 勤務地
- 給与・待遇
- 福利厚生
これらの情報があいまいだと、人材に「この会社に応募して本当に大丈夫かな…」という不安を与え、応募をためらわせてしまうため、必ず明記しなければなりません。
また求人票を魅力的に見せるポイントとして、職場環境を把握できる文言や写真を掲載することも挙げられます。これらの情報は、「欠員補充の理由が職場環境に起因しているわけではない」ことのアピールにつながり、結果として人材に安心感を与えられます。
関連記事:あれもこれも”詰め込んだ求人票は逆効果!転職希望者にあわせた「求人票を分ける」メリットを解説
ポイント2.目的に応じた採用手法を選定する
数ある採用手法の中から、自社の目的に合うものを選択することも、欠員補充で意識したいポイントの一つです。
企業が人材を募集する手法は、人材紹介サービスやダイレクト・ソーシングなど多岐にわたります。それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解した上で、自社にとって最善の手法を選択すれば、欠員補充の効率化を図れるでしょう。予算や採用までのスピード、確保できる工数などを加味して、どの手法が適しているのかを見極めたいところです。
採用手法の種類やその特徴は、以下の記事で詳しく紹介しています。
関連記事:【採用手法一覧】中途採用に役立つ採用手法の種類や比較などを総まとめ
ポイント3.採用プロセスを最適化しスピーディーに対応する
欠員補充を効率的に行うには、採用プロセスを見直すことも有効です。
採用プロセスとは、採用活動全体の流れのことです。これを最適化することで、採用にかかる費用や工数を削減できます。また、より多くの応募への対応が可能となるため、求める人材とマッチできるチャンスも広がります。
実際に採用プロセスを見直す際は、無駄な工程がないかどうか、そして費用対効果がより高い方法がないかどうかを検討すると良いでしょう。
関連記事:採用フローとは?新卒・中途の違いや運用のポイント、注意点を解説

欠員が発生したときの対策
続いて、欠員が出た際に企業ができることを、2つのケースに分けてご紹介します。
欠員時の対応方法
- 対策1.新入社員の早期離職の場合
- 対策2.中堅以上の社員の離職の場合
対策1.新入社員の早期離職の場合
新入社員がなかなか定着しないのであれば、企業文化やフォロー体制に問題がある可能性が高いといえます。再発防止のためには、離職する社員へのヒアリングを行って共通する原因がないかどうかを探り、問題点を改善していくことが肝心です。
新入社員が早期離職してしまう主な要因としては、入社後のギャップや人間関係などが挙げられます。採用フローの中で業務の難しい面もしっかりと説明する、またはメンター制度を活用して手厚くフォローするといった取り組みで、早期離職のリスクを減らしましょう。
対策2.中堅以上の社員の離職の場合
社歴がある程度長い社員の離職が続く場合は、業務負担や待遇、キャリアアップの選択肢などに問題があるのかもしれません。対策の第一歩として、新入社員の場合と同様に、退職面談でヒアリングを行うことをお勧めします。その後全体の業務量や社内ルールを今一度見直し、離職の要因を少しずつ改善していくことで、再発防止につながるでしょう。
また、こうした社員の離職は、残された社員のモチベーションの低下を招く恐れがあります。離職者を連鎖的に増やさないためには、社内アンケートや個別面談を通して、会社への不満がないかどうかを定期的に確認することも有効です。
欠員を出さないための対策
最後に、欠員が出る前に実施できる対策を見ていきましょう。
欠員を予防するための取り組み
- 対策1.コミュニケーションを活性化させる
- 対策2.労働環境を見直す
- 対策3.社員のメンタルヘルスケアを行う
- 対策4.教育制度や人事評価制度を見直す
対策1.コミュニケーションを活性化させる
社員同士のコミュニケーションを促進させことは、欠員を防ぐための効果的な対策です。具体例としては、以下のような取り組みが挙げられます。
コミュニケーションが活性化するためにできること
- チームミーティングを定期的に行う
- メンター制度を導入して1on1を実施する
- 社内イベントを実施する
こうした取り組みを行うことで、社員同士の信頼関係が深まります。その結果、心理的な安心感が生まれて従業員エンゲージメントが高まり、離職抑止にもつながるわけです。
ただし、コミュニケーションを活性化させたいからといって、業務外での交流を強制してはなりません。プライベートを重視する社員にとっては、かえってストレスとなってしまうためです。あくまでも、自主的に交流できる機会を設けることに注力しましょう。
対策2.労働環境を見直す
欠員を出さないためには、適正な労働環境を整えることも重要です。実際には、以下の取り組みを行うと良いでしょう。
労働環境を改善するためにできること
- 快適なオフィス環境を提供する
- ワーク・ライフ・バランスを整える
- 福利厚生を見直す
- 労働時間を適正化する
労働環境が整備されていなければ、社員の不満やストレスがたまるため、離職の可能性が高まります。それどころか、万が一ハラスメントや長時間労働が横行している場合は、社員の心身の健康を損ないかねません。
労働環境に関するアンケートを行う、もしくは社内ルールや各社員の労働状況を見直すなどの対策によって、はたらきやすい環境を整えたいところです。
対策3.社員のメンタルヘルスケアを行う
メンタルヘルスケアも欠員対策の一つで、具体例は次の通りです。
社員のメンタルヘルスケアのためにできること
- ストレスチェックを定期的に実施する
- カウンセリングサービスを提供する
- 産業医との連携を強化する
- 休職している社員への復帰支援を行う
社員のメンタルヘルスケアは、企業にとって欠かせない取り組みです。これをおろそかにすると、パフォーマンスの低下を招いて生産性が落ちる上に、離職率の増加も引き起こします。こうしたリスクを回避するためにも、上記の対策を取り入れて社員の心の健康を守りましょう。
なお2015年12月からは、厚生労働省が定める「労働安全衛生法」によって、常時50人以上の社員を雇用する事業場でストレスチェックの実施が義務付けられています。違反した場合は行政指導の対象となるため、遵守しなければなりません。さらに50人に満たない事業場に対しても、努力義務として実施が推奨されています。
このように、社員のメンタルヘルスケアは国からも重要視されているのです。
(参照:厚生労働省東京労働局『ストレスチェック制度について』)
対策4.教育制度や人事評価制度を見直す
社員が教育制度や人事評価制度に対して不満を持っていると、欠員を招いてしまう可能性があります。対策として、以下の取り組みを行うことが大切です。
教育制度や人事評価への不満をなくすためにできること
- 入社時の研修プログラムを充実させる
- 人事評価基準の透明化・公正化を図る
- スキルアップを目的とした研修を行う
- キャリアプランを設計するための面談を行う
教育制度や人事評価制度が適正でない場合、社員は「会社から大事にされていない」「やりがいを感じない」といった不満を持つようになります。制度が見直されない限り、その不満は徐々に大きくなってモチベーションの低下を加速させるため、離職率が増加してしまいます。
スキルアップの機会を平等に設けた上で、適正な基準で社員を評価し、従業員エンゲージメントを高めることが欠員を予防するポイントです。
欠員補充には人材を確実に集めるための工夫と、迅速な対応が求められる
欠員補充を行う際には、魅力的な求人票を作成する、また適切な採用手法を選定するなど、新たな人材を迅速に採用するための工夫が求められます。空いたポジションをすぐに埋めなければ、業務に支障を来す可能性があるためです。
また企業側は、欠員補充を行わずに済むような取り組みを日ごろから行うことが理想です。コミュニケーションの活性化や社内制度の見直しによって従業員エンゲージメントを高め、離職抑止に努めましょう。
「欠員補充を確実に成功させたい!」という人事・採用担当者は、「doda」にぜひご相談ください。「doda人材紹介」や「doda ダイレクト」など、幅広いニーズにお応えできる多様なサービスを提供しております。
中途採用なら総合支援サービスdoda
doda採用支援サービス一覧

採用コスト削減につながった
doda導入・採用成功事例
おすすめ記事
欠員補充とは?対応手順や欠員を出さないための対策方法を解説ページです。【中途採用をお考えの法人様へ】dodaサービスのご案内 - 採用成功への扉を開く、総合採用支援サービス